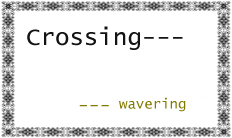 |
||||||
二人が公園を抜ける間に、夜の帳は下り、辺りはすっかり暗くなっていた。ぽつぽつと灯る街灯。家々の明かり。アンドレには当たり前の風景だ。それをオスカルは、やはり明るすぎる、と言う。 約束の時間まで、残すところあと数時間となった。日が落ちると気温が急激に下がり、昼間と同じ格好では凍えてしまいそうになる。アンドレはオスカルの部屋に戻ろうと思い、横を歩く彼女に声をかけようとした。 オスカルはうつむきながら歩いていた。薄暗がりの中では、表情が伺いにくくて彼女が何を考えているのかわからない。何かを一心に考えているようでもあり、悲しそうでもある。少なくとも、アンドレにはそう見えた。 「オスカル」 アンドレが声をかけると、彼女は顔をあげた。「なんだ?」と答えたその表情に、暗い影はもう見られなかった。 「戻ろうか」 アンドレが切り出すと、オスカルは「ああ、そうだな……」と答えたものの、少しだけ残念そうな顔をした。 「もっと街のほうにも行ってみたかったな。パリはどうなっているのだろう。時間さえあったら、もっとこの世界のことを知りたかったのに、アンドレ」 彼女は、自分の選んだ方向が悪かったからだがと苦笑した。 そんな顔を見ると、アンドレは困惑してしまう。頼むからそんな顔しないでくれよと、心の中で哀願する。 彼女がパリの中心とは反対方向を選んで歩き出した時、正直ほっとした。今でもその気持ちに変わりはない。だが、悲しそうな顔をされると、自分が何か、悪いことでもしてしまったような気持ちにさせられる。 そんな表情をするオスカルにアンドレは弱いのだ。たとえ彼女が、自分の知っているオスカルでなかったとしても、それは変わらなかった。 アンドレが彼女の手を唐突に引いた。 「行こう」 “どこへ”とオスカルが尋ねるよりも早く、アンドレは、彼女の手を掴んだまま、右手を上げると、歩道から車道へ一歩踏み出していた。車のライトに照らされて、彼のシルエットがくっきりと浮かび上がった。 二人はアンドレが止めたタクシーに乗り込んだ。アンドレが行き先を告げると、車は再び走り出した。車窓に、街の灯りが流れ出す。 いつもアンドレは思う。窓から見える街は、まるで映画のシーンのようだと。そこには確かに息遣いが感じられるのに、手を伸ばしても掴むことができない。オスカルはどう感じているのだろう。熱心に風景に見入っている彼女の背中で揺れる金色を見て、アンドレは想像する。 黒のセダンは、しばらく走るとセーヌ川沿いのプレジダン・ケネディ大通りに出た。通りに出たとたん、遮るものがなくなって、目的地がよく見えるようになった。尖った先端が空を貫くようにそびえる鉄の建造物、パリの象徴ともいえる巨大な鉄の貴婦人。 アンドレが運転手に告げた場所は、エッフェル塔だった。 エッフェル塔は、オスカルのアパルトマンからそう遠くない場所にあり、そこからならパリを一望できる。この時代の最後の思い出に、せめてパリを遠景からでも見せてやりたい。アンドレはそう考えたのだ。 車はミラボー橋を横目にして通り過ぎ、つづいてグルネル橋そばの自由の女神も通過した。ニューヨークにある像のレプリカだ。そのオブジェを見ても、オスカルには、どうという感慨はなさそうに見えた。しかし一方のアンドレは、女神が手にした銘板に書かれている文字のことを思うと、複雑な思いだった。 刻まれているのは、人類史上不滅の1789年7月14日。 フランス革命が勃発した日だ。立ち上がった民衆がバスティーユ牢獄を襲撃した日。そして、彼女が命を落とすことになる日。 オスカルが過去に戻ったとして、それからのフランスが、どんなうねりに飲み込まれて行ったのか、その歴史が辿った道筋を、この国の人間であれば知らぬ者はない。もちろんアンドレも十分に承知している。 もう見えなくなってしまった女神像と、目の前の女性の姿が、アンドレの中で重なる。 革命がどれほど血に汚れ、紆余曲折して当初の理想とかけ離れて行ったとしても、その日、理想と自らの信条に命を捧げたオスカルは、未来をまっすぐに信じていたに違いない。彼女はそういう人間だ。アンドレにはよくわかる。 エッフェル塔に近づくにつれて、大通りは渋滞してきた。渋滞自体はいつものことだが、今日は外せない約束があるとあって、アンドレは手首のクロノグラフをちらちらと見ては、時間を気にしていた。このまま大通りを進むより、早々に向こう岸に渡ってしまった方が少しは速いような気がする。彼がエッフェル塔の真正面にかかっているイエナ橋の一本手前の橋でセーヌを渡るように言うと、運転手はウィンカーを出して右折した。 二階建て構造のこの橋は、下を歩行者と車が通り、その上をメトロ6号線が走っている。橋の上は、車はそこそこ走っていたが、歩いている人の姿は見られなかった。 川の半ばまで来た時、地下鉄が頭上を通り過ぎた。轟音と振動が鋼鉄の橋を伝わる。優美な曲線を描く鉄柱が軋み、吊り下げられたレトロなランプのオレンジ色の灯が揺れた。 音と振動に驚いたオスカルは身を縮め、アンドレの方に体を引いた。思いがけず、彼の胸に飛び込むような体勢になる。アンドレは彼女の体を抱きとめた。 地下鉄が通り過ぎると、すぐにオスカルは「離せ」と言って、アンドレの手を払いのけた。払いのけた手の力は弱く、声は小さくかったが、アンドレは慌てて両手を広げる。オスカルはシートに座りなおすと、また車窓に顔を向けてしまった。少し頬が赤く染まって見えたが、それは、彼女の顔をオレンジ色の光が照らしていたからかもしれなかった。 ほどなくして、二人はエッフェル塔の足元にたどり着き、車を降りた。 間近に見るエッフェル塔は彼女の想像をはるかに超えていたようだった。300メートルを超える巨大なモニュメント。弧を描く太い鉄骨に、ワイヤーのような無数の鉄線が絡みつくようにして、その重量を支えている。天を貫かんとする四角錘の鉄塔は、夜になるとライトアップされて、その存在を昼間よりも誇示しているように見える。「鉄の貴婦人」とは、建設当初、揶揄して付けられたあだ名だが、きらびやかに着飾り、夜会に出かける貴婦人の様子を思うと、言いえて妙である。 アンドレが清算をすませてタクシーを降りると、彼女は、頭上はるかにそびえ立つ鉄塔を見上げて立ちつくしていた。彼女の時代には想像もつかなかった威容だろう。アンドレが肩をたたくと、オスカルは呆気に取られている様子を見られたのが気に障ったのか、また怒ったような顔になった。見くびられたり、馬鹿にされたりするのが死ぬほど嫌いなのだろうか、彼女は。アンドレにはそんなつもりは全くなくて、素直な彼女の感情表現を見るたび、ただ可愛いと思い、むしろ嬉しささえ覚えるのだが。 ふと、アンドレは出会ったばかりの頃のオスカルを思い出した。まだ気心の知れない頃の彼女は、ちょうどこんな風だった。彼女の生まれもった気位の高さと、それに隠されたイノセンス。いつの間にか、それが彼を虜にしてしまっていた。――いや、いつの間にかではない。たぶん、出会った瞬間からだったと思う。 アンドレは自分の考えに、わずかな動揺を覚えた。だんだんと彼の中で、過去から来たオスカルと、自分の恋人であるオスカルが混じり合って来ていた。いっしょに過ごしていると、二人の区別があいまいになっていき、距離感と不思議な親近感が、ないまぜになる。 気がつくと、オスカルが小首をかしげ、怪訝そうにアンドレを見ていた。 「時間がない。行こうか」 アンドレは自分に言い聞かせるように、“時間がない”の部分をわざと強調して言うと、展望台につづくエレベーターの乗り口に向かった。 三層構造になっている塔の一階部分を経由して、地上115メートルの第二展望台に辿り着く。そこに広がるのは360度のパノラマだ。オスカルは感嘆のため息をもらす。ここから眺める現代のパリは、観光名所がライトアップされた光の洪水だ。 「ヨーロッパ中の金銀財宝を集めても、これほどの輝きは作れないだろう」と、彼女は目を輝かせながら、ぐるりと屋外の展望スペースを一周した。眼下には、セーヌ対岸にシャイヨー宮、その反対側には、シャン・ド・マルス公園や旧陸軍士官学校にアンヴァリッドが見えていた。それらの歴史的な建物も、今は溢れそうな光の一部に収まって、近代的なビルと並び立ちながら、パリの風景を形作っている。 塔の東側で、オスカルが立ち止まった。シャン・ド・マルス公園の向こうに旧陸軍士官学校が見える方角だ。 夜景だし、220年以上も前の風景と、現在のそれでは全く違うから、見せても大丈夫だろうとアンドレは考えていた。これほどの高所から、パリの全景を見た経験だって、彼女にはないだろう。だが、旧陸軍士官学校は彼女も通った場所だったかもしれないし、さきほどの会話にシャン・ド・マルスの名前も出てきていた。何か勘付いてしまっただろうか。 セーヌ川にかかるアルマ橋の方から来た北風が、彼女の長く豊かな金の髪を、高い金網の柵に容赦なく叩きつけていた。 「オスカル……?」 アンドレが様子を伺うようにして呼びかける。名前を呼ばれて彼の方を見たオスカルに、特に変わったところはなさそうだった。 アンドレは胸をなでおろすと、彼女に訊いた。 「まだ上があるけど、どうする?」 「もちろん、行く!」 オスカルはためらいもなく、答えた。 この先は、さらに150メートル以上を昇る。もっと天に近づく。 セーヌの流れに平行して、オレンジ色のテール・ランプが、もう一本の河のようになって流れていた。その中のひとつにアンドレとオスカルも含まれていた。 約束の時間まで、あと2時間ばかりを残して、二人はようやくオスカルのアパルトマンへの帰路についていた。 オスカルは、タクシーの後部座席でアンドレの肩にもたれて、うとうとし始めていた。車の揺れが心地よいのだろう。今日はたくさん歩いたし、いろいろと見た。彼女にとっては、頭の整理がつかなくなるくらい膨大な情報量だったことだろう。それに、昨夜はほとんど寝ていないと言っていた。わずかな時間でも、こうして少し休んだ方がいいと、アンドレは彼女の無防備な寝顔を見ながら思った。 彼女のやわらかな寝息。軽く閉じられた唇。それがこんなにも近くにあるというだけで、アンドレはこれ以上ないくらいの幸福を感じる。かつての自分もそうだったのだろうか。 そっと彼女の顔に左手を伸ばす。頬にかかった髪をどけてやりたかった。 オスカルの目が、ふいに開いた。アンドレは驚いて手を止める。 「なんだ、起きてたのか」 オスカルが上目遣いに彼を見た。 「……人間は、どこまで高みに上れるものなのかな、なあ、アンドレ」 いきなり哲学問答か、そんなことおれに訊かれてもと言いながらも、アンドレは目を細めた。 「おまえの方が答えをしっているんじゃないか?」 オスカルはそれには答えずに、また目をつぶってしまった。そして、そっと彼の方に寄り添うと、わざと胸の方まで頭を傾けて言った。 「今度、あいつの傍でも、寝たふりしてやろうかな」 ふふっと微笑まれて、アンドレはどう答えてよいかわからず、ただ彼女といっしょに、車の規則的な揺れに身を任せた。 彼女がもたれかかっている部分が、何だかくすぐったくなって落ち着かなくなった。 オスカルの部屋に戻り、アンドレの心づくしの夕食を共にして、二人が例の鏡の前にようやく立ったのは、約束の時間まで、わずか30分を残した時だった。 夕食後、オスカルの方がやきもきするくらい、アンドレはどこか動作が鈍くて、目は合わせないし、話しかけても生返事だった。その上、いつまでたっても、なかなか鏡のある部屋に行こうとしない。 とうとう痺れを切らしたオスカルが「行くぞ」と席を立ったのが、ついさきほどのこと。 「おまえには、いろいろと世話になったな。感謝している。こう言うのも奇妙だが、おまえのことは忘れない」 オスカルは自分の世界に戻れるからだろう、実にさばさばと別れを告げる。 対してアンドレの方は、何だかそわそわと落ち着きがない。 「時刻は?」 尋ねられたアンドレがクロノグラフを見る。 「8時……40分」 「あと、20分か。問題ないとは思うが、いざとなると緊張するな。昨夜と同じようにすればよいのだったな。たしか、こう……」 思い出しながら、オスカルが鏡に両手のひらを当てた。鏡には、こちら側の二人の姿が映し出されている。手前にオスカルがいて、その背後にアンドレがいる。彼の顔はこわばっていた。自分よりもアンドレの方が、よっぽど思いつめた顔をしているので、オスカルは、おかしくなって、振り返った。 それが引き金になった。アンドレの口が開く。 「オスカル……未来を、知りたくは……ないか?」 (つづく) |
||||||
|
||||||