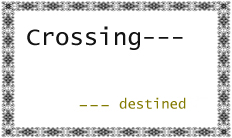 |
|||||
彼女の身に異変が起きていると知った時、自分がパリに戻っていたことが功を奏するだろうと、彼は思った。一人でいたら、もっとひどいパニックに陥っていたかもしれないし、あちこち歩き回った挙句に過去には戻れなくなり、時間の迷い子となって、挙句、歴史も大きく変わってしまったかもしれない、と。 だが、違った。むしろその逆だった。アンドレは内心で舌打ちする。歴史に介在する要素として、自分が最大のネックだったのだ。 たとえ、目の前のオスカルが自分のオスカルでなかったとしても、自分は救わずにはいられないのだから。――彼女がオスカルである以上。 言ってしまう前から、すでに後悔ならしていた。だが、言わずにはいられなかった。それが自分という男なのだと、いまさらになって気づく。 天井で煌々と輝くライトの明かりが、やけにまぶしい。喉が渇く。口に出してしまった言葉は、無かったことにはできない。 彼女にここが未来だと告げ、これから彼女の身に降りかかることや、フランスが辿る道を知らせれば、あるいは彼女は天寿をまっとうできるかもしれない。だが、それと引き換えに、未来にどれだけの影響が出るのかは、計り知れない。 そんなことは、彼女に嘘をつこうと決心した時点から分かりすぎるほどに、分かっていたはずだった。だが、どうしても、このまま彼女を過去に帰すことが、アンドレにはできなかった。 今ならわかる。もし、地球の存亡とオスカルの命、どちらを取るかと選択を迫られることがあったら、おそらく自分は迷わず、オスカルの命の方を選ぶだろう。 この場に自分がいないければよかったのにとアンドレは思った。よりによってオスカルの誕生日にブリュッセルにいるなんて、何の因果かと嘆きながら、あのまま予定通りに過ごしていれば。 もしかしたら、骨董店での時計との出会いも、その片割れが遠い異国に眠っていることが、あの時になってわかったのも、時の秩序を守るために、モイライがはからったのではないかとさえ思えてくる。あるいは彼女自身が(時計はフランス語で女性名詞)、時の女神の化身だったのかもしれない。 神々の長であるゼウスでさえ逆らえないという彼女達に、一握の塵に帰す運命の人間である自分が、抗った結果が、これだ。 もっと驚くかと思っていたが、オスカルは、アンドレが拍子抜けするくらい冷静な顔をしていた。もしかすると、今の自分の言葉が理解できていないのかもしれないと、アンドレは噛んで含めるように説明し始めた。もう時間がない。 「いいか、オスカルよく聞いてくれ。ここはおまえ達が生きた時代から200年以上たった世界で、おまえ達はこれから……」 オスカルの表情がみるみる険しくなる。ようやく事態が飲み込めたのか、それともアンドレに騙されたことがわかって怒りを覚えたのか。だが、謝っている時間的余裕はない。アンドレは残された時間内に、出来るだけ彼女に情報を伝えようと、それだけに集中することにした。 すると、オスカルは眉間に右手を当ててうつむいた。待てというように左手をアンドレの鼻先に突き出し、深くため息をついた。心底あきれたような声で言う。 「おまえは、どうしていつも、そうなのだ……?」 アンドレは口にしようとしていた言葉を飲み込んだ。オスカルは何を言っているのだろう。 「それを言ってしまったら、おまえのこれまでの努力が水の泡だろうが」 極度に緊張していたからだろうか、それとも思考を集中させていたからだろうか。アンドレは一瞬、オスカルの言っている意味がわからなかった。 “努力が水の泡?それはどういう――?” 背中に電流が走ったように感じ、アンドレはようやく彼女の言わんとしていることを理解した。冷や汗が噴き出す。 「それって、まさか……まさか、ここが未来だと知っていたという――」 オスカルは黙ってうなずく。 「……いつから?」 ようやく搾り出すようにして、アンドレが訊く。 「ショヴィレが、ここを訪ねて来た時から」 アンドレの体から力が抜ける。 「わたしは軍人だ。いくら眠っていても、気配が変われば目が覚める。ましてや隣室で話し声などすれば、跳ね起きるさ。そういう風に訓練されている」 アンドレは思い出す。老人が置いていった手紙を読み終えたときに、寝室で物音がしたように思ったが、あれは気のせいではなかったのだ。オスカルはドアの向こうで一部始終を聞いていて、全てを理解したに違いない。 手近に置いてあったスツールに、アンドレは背中を丸め頭を抱えて座り込んだ。つじつま合わせに苦しい説明をした時にも、彼女が異論を差し挟まなかったのは、そういわけか。 「とんだピエロというわけだ」 アンドレが吐き捨てるように言うと、オスカルは彼の肩に手を置いた。 「そう、落ち込むな。おまえはよくやっていた」 なぐさめられて、アンドレは一層うなだれる。 「……すぐに立ち直るから、まずは落ち込ませてくれ」 「うん」 数十秒がとても長く感じたが、アンドレはようやく顔を上げると、再度尋ねた。 「それで、おまえは未来を知りたいとは思わなかったのか?」 彼を見下ろすオスカルが、静かに首を横に振った。肩先で金の髪が揺れる。 「知らせない方がいいと判断したのだろう?ならば、わたしはおまえの判断に従うだけだ。わたしは、おまえを心から信頼している。もし、おまえが毒杯を差し出したとしても、迷わず飲み干すくらいに。そのおまえが見せてはいけないと判断したのならば、わたしはあえて目をつぶろう」 彼女の言葉がアンドレの胸を打つ。過去の自分に寄せる彼女の信頼の深さを思った。こんな時なのに、心が震える。 「騙そうとしたりして、すまなかった」 「いい、謝るな」 彼女はアンドレの顔に手を伸ばし、そっと額にかかった髪の一房に触れ、左目が隠れるように寄せてみる。 「謀(はかりごと)も裏切りも、宮廷ではありふれたことだ。慣れている。だが、おまえに嘘をつかれる度に、正直、胸が痛んだ。それが必要なことであったとしても――」 オスカルの指が黒髪を巻きつけて強く引っ張ったので、アンドレは軽い痛みを感じる。 「――おまえだけはいつも、わたしに誠実であってほしいと。隠し事や嘘はご免だ。おまえにだけは嘘をつかれたくない。だから、腹いせに、わざとわがままを言って、気ままに振舞って困らせてやった。……わたしの方こそ悪かったな」 アンドレから手を引く際、オスカルの指がかすかに彼の頬をなぞった。アンドレは首を振る。 もう一度「すまない」と謝って、彼女の手を取ると、手の平に触れるか触れないかの淡い口付けを落とした。彼女は大人しく彼のなすがままに任せていた。 「制限された中でも、おまえは、わたしに出来るだけのものを見せてくれた。ここは、我々の時代よりも、ずいぶん自由な世の中になっているのだな」 オスカルが部屋をぐるりと見回しながら、今日起きた出来事に思いを巡らす。 「わたしたちの時代が、ここにつながっていて」 もう一度、アンドレと目を合わせ、オスカルは鏡の前に立った。鏡に映る姿が、もうわずかに細波立っている。 「自分がこれからするかもしれないことの一部が、この世界のどこかに息づいているかもしれないと確かめられたから、安心して帰ることができる。――ありがとう。何より、おまえが、こっちではよく笑っているから」 彼女は鏡のガラスに両手を置いた。アンドレがスツールから立ち上がる。 自由、平等、博愛。 そのほんの一部しか、見せることができなかったけれど、彼女は――…。 「未来など詳しく知らない方がよいのだ。おかげで、わたしは心のままに振舞える」 鏡に彼女の顔が映っていた。微笑む彼女を、ただ美しいとアンドレは思った。 オスカルは目を閉じた。アンドレが後ろで何か言っているのが聞こえる。 「国の未来もだが、自分のことも大切にして。何が大事なのか、自分の心の真実から逃げないでくれ。そばにある大切な……」 彼の声は、そこで聞こえなくなった。 鏡に触れたところが温かくなって、そこからするりと内部に入り込んだと思うと、無音の暗いトンネルのような空間を抜けて、誰かとすれ違った。それから、どこかにすとんと落ちて、つづいて、しっくりとはまった感覚がした。 目を開ける。 さっきまでと比べて、ひどく暗い。目が慣れる前に、オスカルは背後から声をかけられた。 「オスカル?」 聞き覚えがあるのに、懐かしい響きのする声だ。オスカルの胸の辺りがじんわりと温かくなる。こちらでも、彼は自分の側にしっかりついていて、そしてサポートしてくれていたのだと分かる。 「アンドレ」 振り返ると、険しい表情の彼がいた。顔の片側は、さきほどまで一緒にいた”アンドレ”と違って、波打つ黒髪で隠されている。 オスカルは、ゆっくり彼に近づくと、顔に手を伸ばし髪に触れた。アンドレは身動きすることもできずに目だけで彼女の動きを追っていた。 はかない望みを抱いて、そっと彼の髪をかきあげてみる。彼の左目が本当に永遠にふさがれてしまっているのかどうか。 確かめたくなって、手を伸ばしてみて。確かめられたことは、彼の目が固く閉ざされて二度と開かれることがないということだった。思い知らされただけだった。 「オスカル?」 アンドレは訝しげに彼女の名を呼んだ。 「ああ、すまん」 オスカルは、慌てて手を引っ込め、一歩後ずさりした。 どうやら収まるべき所に収まったらしいと、ようやくアンドレが安堵の表情を浮かべる。オスカルもほほえみ返した。 だが、お互いに言葉がつづかない。 オスカルは、ふと。 ”未来にも私とおまえがいて……そして……” そう言ってしまいたくなる衝動にかられたものの、言葉を飲みこんだ。 未来で二人が恋人同士だとして、それが彼にとって救いとなるのか、それとも絶望を深めるだけなのか、彼女にはわからなかった。 縁談が持ち上がってから、まださほどたっていない。プロポーズは断ったものの、アンドレには、詳しい経緯を伝えていない。自分の気持ちも……。彼がまた自らの感情を封じ込めたのをいいことに、自分は答えを保留しているのだ。 もし、今、彼と自分が平等な世界に身を置いていたとしたら、自分は彼の気持ちに応えるのだろうか。 パリで暴徒に襲われた時に味わった喪失の恐怖と、今朝、あちらでアンドレに唇を奪われた時によみがえった甘やかな感覚がオスカルの体を駆け抜けたが、それでもまだ答えを口に出せない。 「おまえは、やっぱりおまえだ」 「なんだよ、それ」 オスカルが上目づかいにアンドレを見る。しばし見つめ合った後で、ほぼ同時に噴き出していた。わけもなく笑う。目尻には涙が浮かぶ。それからひとしきり、何がおかしいのか分からないまま笑い続けた。 こうして、二人で声を出して笑い合ったのは、いつぶりだろう。 やっと笑いが収まったところで、目を見交わした。互いに急にまじめな顔になる。 オスカルが彼の手を取ると、自分の指を絡めた。ぎゅっと握る。アンドレもその手を握り返した。しばし手をつないだまま見つめ合う。 「戻ろう」 そう言ったのは、アンドレの方だった。 梯子を降りる前に、アンドレが例の鏡に、埃よけの布を被せようとして、今一度それを見た。二人の姿が映っている。 鏡に覆いを被せてから、先にアンドレが梯子を下りた。オスカルは一人、心の中で思いを巡らせながら、布をかけられてしまい、もう何も映さない鏡を振り返り、それからアンドレにつづいて梯子を下りた。 アンドレはオスカルを部屋の前まで送り届けた。彼女が部屋に入る。何だか不思議と何年も留守にした後のような懐かしさを感じる。ふと見ると、居間のテーブルの上に見慣れない箱が置いてあった。蓋を開ける。中にはベルベットのケースが二つ収められていた。 「ああ、それ。ジョベールから、おれ達に、例の一件のお礼にと贈って来たプレゼントだ」 「ジョベール……!」 慌てて二つのケースを取り出すと、二つとも蓋を開けてみる。よもやと思ったが、ジョベールはもともと優れた時計技師だ。 中には、似たような時計が二つ。見覚えがあった。間違いない、未来のアンドレのコートのポケットに入っていたのと全く同じデザインだった。 時計の蓋を開けて確かめてみる。文字盤にはジョベールの銘がしっかりと刻まれている。未来で見たのと同じ字体で。 18世紀に自分とアンドレのために作られたものが、めぐりめぐって、再び未来の自分達のところまでたどり着いていた。 オスカルの青い瞳から涙が溢れ出した。 「どうしたのだ?オスカル」 心配したアンドレが声をかけたが、彼女自身もなぜ、自分が泣いているのか分からなかった。ただ、涙がこぼれ、こみ上げる感情を抑えることができない。 突然泣き出した彼女を気遣って、アンドレが彼女に近づき肩に触れた。そこから、彼のぬくもりが沁みて来て、熱となって心臓まで届いたような気がした。 「アンドレ……わたしは……」 二人のかたわらでは、懐中時計が精確なリズムで時を刻んでいる。 その時計は、未来では、まだ止まったままだった。 (了) |
|||||
|
|||||