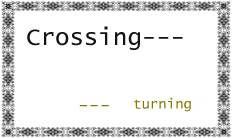 |
||||||
アンドレがオールを体に引き寄せると、ボートは湖面を滑るように進みだした。 まだ時間があるからと言われて、オスカルが指差したのはアンフェリウール湖の桟橋につながれていたボートだった。 貸しボートの受付で暇そうにタバコをふかしていた老人に料金を支払うと、二人は、もやい綱を解いてもらってボートに乗り込んだ。 はじめ、オスカルがオールを操る方に座ろうとしたので、アンドレが止める。 「漕ぐのは男の仕事だよ」 「なんだ、この時代、男女平等ではないのか」 オスカルはそれくらい、わたしにも出来るぞと言い張るが、ここはアンドレも譲らなかった。 「たまには格好つけさせてくれって、ただそれだけのことさ」 アンドレがオールを動かすたびに、ボートは水面をえぐるようにして、ぐんと進んだ。 オスカルに、それならばお手並み拝見だと、からかい気味に言われて、アンドレはコートを脱ぐとシャツの袖をまくって、勇んで湖に漕ぎ出した。 アンドレが渡してくれたラベンダー色のストールを羽織ったオスカルは、一漕ぎする度に揺れるボートのへりを片手で掴み、反対の手でストールが飛ばされないように胸元を押さえながら、真正面に座るアンドレの動作を見つめている。湖面を冷たい木枯らしが渡り、彼女の金髪をかすかに揺らす。アンドレは力強いストロークを刻んでいく。 夏場ならばたくさんのボートが浮かんでいるはずの湖上だが、この寒い時期に舟遊びをしようなどと考える人間は、ほとんどいないらしく、他のボートの影は見えなかった。密室でもないのに、不思議と世界に二人だけしか存在しないような感覚に陥っていく。 昨夜から驚きの連続で、少し神経が疲れていたが、船はオスカルがいた世界にも存在するもので、”こちら”も”あちら”も大差はなかったから、彼女の気持ちは、いくぶん安らいだ。 世界にあるのは、風の音と木々のざわめきと、水と空気と光と、そして、彼と自分。 アンドレは黙々とオールを漕いでいる。彼が腕に力を入れる度に、鎖骨が後ろに伸びて、胸の筋肉が張り出す。シャツのしわの変化で、発達した胸の筋肉の動きがわかり、それが腕の筋肉に連動していくのがわかる。それはしなやかな動きだったが、明らかに女性のそれとは違うものだった。 オスカルが重労働をすることはないが、剣を交えているときなど、相手の男の振り下ろした刀身の重さに、違いをまざまざと思い知らされることがある。今、目の前に座る男から感じるのも、それと少しだけ似ていた。 こんなにアンドレの体をじっと見つめたことは、今までなかったような気がするとオスカルは思った。今、自分の目の前にいるのが、姿形はそっくりだけれど、いつものアンドレではないからかもしれない。彼は、しげしげと見つめる対象ではなかった。まるで自分の一部のようなものだったから。あらためて見ると、首もあごも全てが自分とは異質なものだと気づく。通った鼻筋や、唇までも。 “わたしはその感触も、よく知っているはずなのに” 彼の長い指がどんな風に自分に触れるか、そして荒々しいまでに力強く抱きしめると、どんな風にくちづけするか……。 オスカルは自分の肌が覚えている感覚を思い出して、身震いした。それは、さきほど強引に唇をふさがれたときに覚えたものと同質であり、かつて求婚者として名乗り出た男と、図らずも口づけを交わしたときに思い出した感触でもあった。それが呼び起こす、体の奥の方から湧き上がる熱と、とろけるような甘い痺れ。あれは何だったなのか、今でもよくわからない。 アンドレが彼女の顔を見たので、オスカルは我に返って、視線を逸らした。自分は一体なにを考えているのだと恥ずかしくなる。 いつの間にか船は湖の真ん中まで到達していて、アンドレはオールを動かす手を休めていた。 急に顔を背けた理由をごまかすために、オスカルは湖に目を落とし、さざなみ立つ水面をそっと指でなでた。水は指先が痛くなるほどに冷たかった。 まだアンドレは彼女のことを見つめている。 「なんだ、そんなにじろじろと」 怒った口調で言うと、アンドレが謝った。 「あ、ごめん。何だか筋金入りの軍人からイメージしていたのとは、ずいぶん違うから」 「どんな風に?」 「また怒らせるかもしれないけど……」 アンドレは言いよどんだが、オスカルが言ってみろと言うので、つづけた。 「その、無邪気な子供みたいなところが多くて……。もちろん、さっきのトラブルシューティングなんて、さすがだなって思うんだけど。そして今は……」 「今は?」 返事をするかわりに、アンドレはオールをひと漕ぎした。“なまめかしい”というような意味の言葉を言いかけて、やめる。 「おまえが、無遠慮に接してくるからだ。だから子供の頃のように振舞ってしまっていたかもしれない」 オスカルはあいかわらず怒ったような口調になる。 彼をいつもより近く感じていた。身体的な距離ではない。目の前の彼の接し方や口調のせいだろうか。 彼は男女差別もなく、身分もない世界に生きている。それは、子供の頃の二人が互いに抱いていた距離感に近かった。二人はとても近かった。 それに、彼の両目が開いていることも、彼女を常にどこかで責めつづけている罪悪感を、少し軽くしてくれてもいた。彼の左目が永遠に閉ざされた原因を作ったのは自分だ。それが今は、黒い翳りのない二つの瞳がまっすぐに自分を見つめてくれていた。 アンドレの方は意外なことを言われて驚く。こっちはいつもよりよそよそしい距離感にとまどっていたのに、彼女はそれをいつもよい近いと感じている。自分が想像していた以上に、身分の壁というものは厚く、体の奥底から根を張るようにして、過去の自分を呪縛していたのかもしれないと思った。 「わたしが王太子妃づきの士官として出仕するようになった頃からかな。一歩引いてついて来るようになって、それでも二人っきりのときはそうでもなかったのだけど。あの時から、いつも見えない薄い壁を一枚隔てているような感じで」 「あの時?」 オスカルは答えなかった。ただ目を伏せる。 アンドレもそれ以上は訊かなかった。オスカルを自分の部屋に初めて招き入れた時に見た、記憶の断片を彼は思い出していた。何があったのか、それ以上聞かなくても察しはついた。 しばらく会話がつづかなくなって、今度はオスカルの方が気まずく感じ始めた。彼とこうしていると、否応なしに先ほど考えていたことを思い出してしまう。ちらりと彼を見ると、彼女が話し出すのを待っているように見えた。 そこで、ベルサイユのグラン・カナルで王妃と舟遊びしたことや、子供の頃の思い出などをとりとめもなく話しはじめた。こんな風に敷地内の湖で小船に乗って遊んで溺れかけたことがあること、幼い頃は、ばあやの影響か、折にふれて彼が女の子扱いするので、絶交したり、投げ飛ばしたりしたことまであったこと。 「“おれに”とっては、ずっと女の子だったんだな」 アンドレは笑いながらも、それが過去の自分にとって、どれほどの苦しみを伴っていたかを思った。 「おまえ達はどうなのだ?どんな風に子供時代を過ごしたのだ?」 「おれ達はまだ会って一年くらいしかたっていないから、よくは知らないんだ。別々に暮らしているし」 オスカルが思わず、えっと声を出して驚く。それから、少し傷ついたような顔になった。アンドレが、どうしたのだと尋ねると、俯いたまま言った。 「そういうことも……あるのだなと思って」 彼女にとっては想像したこともないことだった。二人が離れて暮らす。常にいっしょにいるのが当たり前で、そんな風に離れて暮らしていることなど、想像できなかった。そういう可能性があることすら、思ってもみなかった。結婚話がもちあがった時でさえ、二人が離れて暮らすことなど考えられなくて。 「で、今は……二人は―…」 いっしょに暮らしているのでもないのに、自由に部屋に出入りできるのだとすれば、関係を訊くまでもなかったが。 「……世界で一番大切な存在さ」 アンドレが慈しむように言葉を紡ぐ。視線を落としたままで、オスカルも呟く。 「……わたし達もそうだ」 だが、彼の言うそれが、自分とアンドレの関係とは同質ではないことを、オスカルは十分に理解していた。 冬の太陽は、もうすっかり西に傾いて、空は茜色に染まり始めていた。この時期の太陽は、母の待つ家に帰る子供のように、この時間になると急に足を速める。日没が近い。 そろそろ戻ろうかと言って、アンドレは船の方向を変えて岸に向かって漕ぎ始めた。黒々としていた湖面にオレンジ色の光が照り返っている。オールが動くたびに水しぶきが弾ける。やがてボートはゴトリと重い音を立てて桟橋にぶつかり、二、三度バウンドすると止まった。二人が戻って来たことに気づいた貸しボート小屋の老人が、桟橋を渡って近づいてくる。 「楽しかった。近頃は、彼と二人っきりになっても、仕事ばかりで、こうしてゆっくり他愛もない話をすることもなかったから、楽しかった」 ここにいる男が彼ではないとわかってはいても、不思議な錯覚が彼女の心を潤していた。図らずも彼と二人きりで、ゆったりとした時間を過ごすことができて、心が近頃には珍しく落ち着いて満たされている。 「王妃様が下さった特別休暇中だったが、これは、この奇妙な体験は、神がわたしに下さった休暇だったのかもしれないな」 ポツリと呟いて、彼女はさびしげに、だがこの上なく美しく微笑んだ。それは黄昏のもつ、はかない光にも似ていて、またアンドレの胸がきしむ。 もうすぐ彼女は元の世界に戻っていく。吹き荒れる革命の嵐、過酷な任務のただ中へ。そしてこのまま何も知らずに戻れば、彼女は、次に巡ってくるはずの誕生日を迎えることなく、死を迎えることも、アンドレにはわかっている。だが、どうすることもできない。 しっかりと係留されてから、アンドレは先にボートから下りて、彼女が下りるのを助けた。彼に向かって腕を伸ばしたとき、岸辺を吹きすぎる風にあおられて、彼女のストールが飛んだ。幸い湖面には落ちずに、岸から一メートルほどのところに立っていた杭にひっかかたので、アンドレが何とか取ろうとしてみたが、うまくいかない。下手に触るとかえって水に落ちてしまいそうだったので、さきほどの老人に手助けを頼みにいくことにする。 ブラウスの上に黒いチュニックドレス姿のオスカルは、寒そうに自分の肩を抱いている。 アンドレは自分のコートを彼女の肩にかけてやると、待っていてと言い残して、ボート小屋に向かって小走りに走っていった。 彼のコートは彼女の体をすっぽりと包み込むように大きく、彼の体温がほんのり残っていた。 彼女の右手がなにか固いものが触れた。彼のコートのポケットの中だ。探ると、そこには懐中時計が入っていた。オスカルは時計を取り出してみると、蓋の細工を眺めてから留め金をぱちんと外し、中を見た。文字盤を見つめる。針は止まったままだった。 彼女はアンドレが戻って来ないうちに、そっと時計を元に戻した。 (つづく) |
||||||
|
||||||