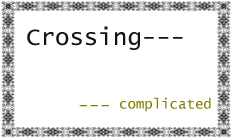 |
||||||
おいしいワインをごちそうするから遊びにいらっしゃいと言って、いつまでも手を振りつづける道連れと別れ、アンドレはRER(高速郊外鉄道)のホームへ急いだ。B線でサン・ミッシェル・ノートルダム駅まで行き、そこからメトロの10番線に乗り換えれば、オスカルのアパルトマンまでは一本だ。 郊外を過ぎ、市街地へと入ると、列車はパリを縦断する。セーヌを横切り、シテ島を過ぎたとき、アンドレは何気なくコートのポケットに手を突っ込んだ。鎖が指に絡む。懐中時計の鎖だ。ブリュッセルで買い求めたものと、対の時計の。指で、時計の蓋に刻まれた、蔓草の細工をゆっくりとなぞる。 この時計をパリの古美術商で見つけたとき、アンドレは一瞬、その場に立ち尽くした。 オスカルの誕生日にプレゼントできるものを求めて、数件の古美術商や骨董品店を回っていた時だ。 蓋に彫られた優美な蔓に、目が釘付けになる。だが、それだけが彼を引きつけたのではなかった。自分でも説明ができなかったが、探していたわけでもないのに街角でばったり旧友に出くわした時のような、そんな感覚だった。 じっと時計を凝視しているアンドレに店主が声をかける。反射的に彼の口をついて出た言葉。 「この時計は、対になるものがあるのでは?」 店主は驚いた顔をしながらも、そうらしいと頷いた。 その時、彼の中に眠る、いつのものとも知れない記憶のどこかが、カチリと音を立てて動いた。 もう一つの時計を求めて、つき動かされるようにブリュッセルまで旅をして、かなり強引なやり方を押し通し、ついにそれを手に入れたのは、どうしても、その時計をオスカルの誕生日までに手に入れたかったからだ。それに、彼女から電話を受けたあと、一刻も早くパリに戻らなければならないとも思ったからだ。 誕生日のプレゼントなのだから、その日までに入手したいというのは当たり前だし、せっかくの彼女の計らいが無駄にならないように、一刻も早く戻りたいというのも自然な気持ちだと思う。 だが振り返ってみると、少々、いつもの自分らしからぬ行動に、ただそれだけが理由ではないような気もして来る。 ポケットの中で、時計はぜんまいを巻き直していなくて止まったままだ。鎖だけが手の中で、小さくしゃらしゃらと音を立てていた。 アンドレの疑念は、何か予感めいたものも伴っていた。 彼はサン・ミッシェル・ノートルダムに着くと、一旦、改札を出た。メトロの駅までは、地上を歩いた方が早いからだ。それに、彼女には明日帰ると伝えてあったから、アパルトマンに着く前に電話を一本入れておきたかった。いくら男勝りとは言っても、女性には準備の時間というものが必要だ。いきなり朝、押しかけて、さらにご機嫌を損ねるようでは、せっかく早く帰って来たのが無駄になってしまう。 携帯の履歴から彼女の番号を選んで発信する。耳に当てた電話からは、呼び出し音が何度も同じトーンを繰り返すのが聞こえる。しかし全く出る気配がなく、ついには留守電の応答メッセージに切り替わった。何度かかけ直してみたものの、結果は同じだった。 アンドレからのコールだということはナンバーで確認しているはずである。すねているだけならいいが。妙な胸騒ぎがした。 彼はメトロに乗り込み、彼女のアパルトマンの最寄り駅まで辿り着くと、改札のターンスティールを弾き飛ばすような勢いで通り抜け、階段を小走りで駆け上がって、彼女の元へ急いだ。 ロビーには顔見知りのコンシェルジュが、いつもの場所に陣取っていて、丁寧にアンドレに挨拶をしてきた。いつもなら一言二言、立ち話をするのだが、今日は軽く手を上げて挨拶を返すと、エレベーターのボタンを押し、開けると同時に滑り込んだ。 オスカルの部屋の前に辿り着く。ベルを鳴らしたが、一向に応答がないので、彼女から教えてもらっていた解錠キーをコンソールに打ち込んだ。ロックが外れると、アンドレはドアを開けて部屋に入り、彼女の名を呼んだ。 「オスカル、オスカル?どこにいる?返事をしろ!」 部屋の中はしんと静まり返っている。まだ午前中だったから、まずはベッドルームを探す。しかし、ベッドはきれいに整えられていて、眠った形跡すらない。不安にかられてリビングの隅々まで探し、カーテンの裏側までめくってみる。だが、彼女の姿はどこにもなかった。バスルームにもキッチンにも、どこにもいない。 出かけているのだろうかと思いかけて、もう一度、ベッドルームに戻った。彼女が物置になっているからと言っていたので、まだ一度も入ったことのない奥の部屋があったはずだ。 ドアを勢いよく開けると、天井のライトが煌々とついていた。部屋の中には、白い布に覆われた家具や調度がまるでオブジェのように並んでいる。オスカルの部屋の設備は手動でもオートでも作動するように作られているが、こうしてここだけライトがついているということは、彼女はここにいる可能性が高い。 壁際を中心に、無造作に置いてある物には、全て白いほこりよけの布がかけられていたが、ひとつだけ、被いが取り去られていているものがあった。それは、大きな姿見だった。年代物のようだ。鏡の周囲は美しい細工で飾られていて、その角に小さな天使の像まで付いている。 その側にあるものが、もぞりと動くのが目に入った。どうやら、人がシーツにくるまっているようだった。 「……オスカル?」 ためらいながら声をかけると、また白いシーツが、もぞりと動いた。まちがいない、彼女だ。そう確信したアンドレは、ゆっくりと布地をはがす。金髪が見えた。うつむいて、心なし体を震わせている。泣いているのだろうか。彼は黙って彼女の肩に手を置いた。しかし、彼女は顔を上げなかった。仕方なく頬に手を伸ばす。あごを捉えて、自分の方に顔を向けさせた。 青い瞳と目が合った刹那、まだ肩にかかっていた布地がはらりと落ち、彼の胸に彼女が飛び込んで来た。彼が抱き止めようと腕を伸ばす。伸ばした彼の片腕を、オスカルが掴んで自分の方に引き寄せた。 その瞬間、アンドレは予想だにしていなかった展開に、頭の中が真っ白になった。 あろうことか、彼の体は宙を舞っていた。彼女が一瞬で片膝を立てたかと思うと、鮮やかに一本背負いを決めていたのだ。自分が投げ飛ばされたことに気がついた頃には、壁にぶつかって、さらに近くにあった家具かなにかの角に、したたかに肩口を打ちつけていた。仰向けに倒れて見上げた天井が、妙に高い。 強い痛みの中で、彼は奇妙な既視感を感じていた。誓って言うが、これまで女性に不埒なことをした覚えもなければ、もちろん犯罪行為を働いたことなどもないから、こんな風にいきなり投げ飛ばされるなんて、生まれて初めての経験のはずだった。学校のJUDOの授業のときにあったような気もするが、誰に投げ飛ばされたのだったか。金髪の青い目をした華奢な体つきの少年――。 「ぼくは男だ!馬鹿にするなら、おまえだって容赦はしない!」 頬を紅潮させて何か怒っていたっけ。あれは……。 「アンドレ?アンドレなのか?」 声をかけられて、我に返る。オスカルが彼の顔をのぞき込んでいた。アンドレは頭を振りながら、ゆっくりと上体を起こした。 「人間って飛ぶんだな……」 「何をばかなことを言っている!大丈夫か?頭を打ったか?」 オスカルは心配そうに、彼の額に手を置いた。彼が彼女を見つめ返す。すると彼女は、びくりとして、手をいったん引いてから、今度は彼の左目にそっと触れた。 「アンドレ……目……」 「ん?目はちゃんと見えるぞ。それより、いきなり投げ飛ばすなんて、いくらなんでもひどすぎないか。……おれがパリにいなくて、そんなに腹が立ったのか?それとも……悲しかった?」 留守にしていた腹いせにしては、少々やり過ぎだとは思ったが、これで彼女も、いくらなんでも気が済んだだろうと彼は思った。オスカルは黙っていた。眉根を寄せて、何か考え込んでいるようだった。 アンドレは彼女の両手首を掴むと引き寄せた。 「は、はなせ!」 オスカルは身をよじって抵抗する。 「いい加減にしないと、おれも怒るぞ」 アンドレはそう言うと、手に力を込めて自由を奪った。彼女の唇を少し乱暴に盗む。彼女は最初、口を引き結んで抵抗していたが、彼がやわらかく唇を押し包み、優しくあやすようにくちづけると、小さな吐息をもらして軽く口を開いた。オスカルの体から力が抜けたのを感じ取って、アンドレが力を緩める。 しかし、彼女はそれを機に、彼の束縛から、するりと抜け出してしまった。アンドレの頬に痛みが走る。 「ぶ、無礼者っっ!」 頬を張った勢いのままにオスカルが叫ぶ。アンドレはひっぱたかれた左頬を押さえながら、初めて、ただ彼女がすねて怒っているわけではないことに気がついた。 「おまえは、おまえは、二度とそんなことはしないと神に誓ったのではなかったか!?……それに、ここは何処なのだ?自分の屋敷にいたはずなのに。なぜわたしは、こんな格好をしているのだ?おまえの……おまえの目は、どうして二つとも開いて……?」 辺りを見回した後、自分の体を見下ろしてから、もう一度彼に視線を戻すと、彼女は真顔でアンドレに尋ねた。 アンドレは、ただオスカルをじっと見つめることしかできなかった。彼自身も彼女の問いに対する答えを持っていなかったのだ。 声も姿形も、確かにオスカルだ。服装も、彼女が以前に身につけていたのを見たことがある。 だが。 ――目の前にいる、おまえは、いったい誰なんだ? (つづく) |
||||||
|
||||||