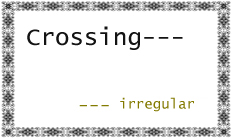 |
||||||
考えあぐねていたアンドレの鼻先をかすめるようにして、寝室のドアが開いた。ふいをつかれて一歩、後ずさる。 薄暗い部屋の中から、金色の髪が現れた。絹糸のような髪は少し寝乱れて、いく筋かが額に張り付いている。白い顔は、寝起きで少しぼんやりしているように見えた。 「なんだ、こんなところに突っ立って」 オスカルは髪をかきあげながら、気だるそうに言った。 「い、いや、ずいぶんと、よく寝ているものだから、様子を見ようかと」 ふーんと曖昧にあいづちを打ち、横目でアンドレを一瞥すると、オスカルは彼の脇をすり抜け、広いリビングを突っ切って行った。ぐっすり眠ったからだろうか、彼女はさっきと雰囲気が違い、だいぶ落ち着いたように見えた。 彼女が出て行ってくれたのはチャンスだった。アンドレは、ちょっと用事があるからと言い残して寝室にすべり込むと、すばやくドアを閉めた。 カーテンを閉めきった室内は探し物をするのに、いささか暗すぎた。カーテンを開けると、一瞬、太陽のまぶしさに目が眩む。 目が慣れてから部屋を一周見渡してみる。ざっと見た限りでは、探している家誌らしきものは見当たらなかった。寝室にはベッドの他、ガラスの扉のついた書棚にサイドテーブル、それに大型のクローゼットがあり、整然としている。 オスカルの部屋は、アパルトマンが契約している清掃業者が、彼女の不在の間にいつも掃除に入っているので、たいてい塵ひとつない。使用人や業者が出入りする生活に、オスカルも小さい頃から慣れているから、大事な物はその辺りに置きっぱなしにしない習慣がついている。 オスカルが使っていたベッドの上には寝具以外は何もなかったが、念のために枕の下を探し、それから書棚に並んでいる本の背表紙に視線を走らせてから、クローゼットを開けてみた。中には服やバッグの他、普段あまり履かない靴の入った紙箱が積み重ねてあるだけで、書籍らしきものは置いていなかった。 サイドテーブルに小引き出しが付いていたのを思い出して調べてみると、黒い革で装丁した本がしまわれていた。金文字で“ジャルジェ家”と箔押ししてある。これにまちがいない。 ここに入っていたのなら、おそらく、さきほど起きたばかりのオスカルの目には触れていないはずだとアンドレは安堵したが、念のために隠しておくことにした。彼は本を取り上げると、クローゼットの中に積んであった靴箱の一番上の蓋を取って中身を取り出し、空いた箱の中にそれをしまい込んだ。 リビングから大音響が響いてきた。 ヘビーメタルの耳障りな金属音にかき消されそうになりながら、うわっというオスカルの小さな悲鳴まで聞こえる。 「どうした?オスカル!」 アンドレが慌てて駆けつけると、彼女は大型TVの液晶モニターの前で、左手にリモコンを持ち、右手で耳を押さえながら、顔をしかめていた。スピーカーからは耳をつんざくようなエレキ・ギターの不協和音が響いている。 「アンドレ、これは、音楽の一種なのか?それにずいぶんと異様な身なりで……」 現代でも受け入れられない世代がいるくらいだから、18世紀の感覚でいえば、音楽としてすら捉えられないのも無理はない。もっとも1980年代に流行ったバンドのライブ映像だから、今となっては、もはや古臭く感じる人間も多いのだが。 画面は客席の後方からのカメラに切り替わると、次々に熱狂する観客のアップを映し出した。 「なぜ皆、あのように頭を激しく上下させているのだろう?」 オスカルが妙なところに関心をもって質問する。 「えっと……あの速いテンポの曲に合わせるためには、たぶんああいう動きが最も自然……だから、かな?」 そういうものだと当たり前に受け入れてしまっていることを改めて訊かれると、答えに窮するものだ。アンドレは、自分でも正しいのかどうか分からないような、自信のない回答をしぼり出した。 先ほどと同様に、ふーんと納得したのかしないのか判然としない返事をすると、オスカルはリモコンのボタンを適当に押し、次々にチャンネルを替え始めた。昨日、落としたときにTVのスイッチが入ったことから、これでコントロールが可能だということを理解したようだ。ただ、片手でリモコンをしっかりと握り、反対の手の人差し指でボタンを押す仕草は、ひどくぎこちなくて、道具の使い方を覚えたての幼児をほうふつとさせた。 アンドレはいつ止めようかと思いながら、内心はらはらしていた。ニュースにドラマに音楽番組にと、ザッピングしているだけで内容までは分からないとは思うが、たまたま歴史チャンネルでフランス革命でも取り上げられていたら、それこそどう言い訳しても通る見込みはなく、真実を話すよりほかなかった。 オスカルの動きが止まった。 モニターには夏の浜辺を歩く男女が映っている。アメリカのドラマのようだ。白いビーチにカラフルなパラソル。俳優達は水着姿で、女性の体を覆っている布は最小限、男性はもちろん上半身裸である。 見ると、彼女は耳まで真っ赤に染めてうつむき、わなわなと震えている。彼女の時代には人前でこんなに堂々と肌を露出させることは、ありえないはずで、ましてや彼女は未婚の身なのだから、全く免疫がないのだろう。 アンドレはチャンスと見て、リモコンを取り上げるとTVを切った。 「いろいろと君の“世界”とは違うだろうから、あまり勝手にいじらない方がいい。君が傷つくことも多いかもしれない」 オスカルは気を取り直して、きっと彼をにらんだが、何も言わなかった。 これ以上、勝手になにかされる前に、アンドレは、まずこの世界の“設定”を説明してしまった方がいいだろうと思った。オスカルには気取られないように呼吸を整える。 「実は……」 「喉がかわいたな」 意を決して話し始めたのに、まだ何も言わないうちにオスカルに遮られてしまった。アンドレの苦労を露ほども知らない彼女は、とても気まぐれに見えたが、仕方なく、彼は飲み物を取りにキッチンに向かった。冷蔵庫を開けると、すぐ後ろで声がした。 「ふーん、すごいな。ここは氷室になっているのか?」 驚いて振り返ると、オスカルがついて来ていて、アンドレの肩越しに庫内をのぞき込もうとしている。 「オ、オスカル、飲み物はすぐに持っていってやるから、リビングでおとなしくしていてくれないか?」 アンドレが冷蔵庫のドアをパタンと閉めてしまうと、オスカルは不満そうに腕組みをし、キッチンのシンクにもたれかかった。彼の顔をやや上目遣いににらみつける。 「なにをそんなに慌てているのだ?何か見られてはいけないものでもあるみたいに」 図星を指されてアンドレはたじろいだが、できるだけ平静を装う。 「そんなことはないさ!……それより、そんなことより、いい知らせだ。実は元に戻る方法がわかったんだ」 おおげさに両手を広げたアンドレは、どこか芝居がかっている。 オスカルは、少し目を見開いてみせたが、思ったよりも冷静に受け止めていた。 我ながら唐突すぎやしないかと、アンドレは自分で自分に突っ込みを入れたくなったが、言ってしまった手前、ここでやめるわけにもいかなかった。 「どうやら、君の住んでいた世界とこの世界は平行世界……いや、別の次元の……えっと何て言ったらいいか」 「要するに異世界ということか?」 しどろもどろになっているアンドレに、逆に助け舟を出すようにオスカルがずばりと指摘する。 「そう、そんなもので、いろいろ共通点もあるけど、それぞれの世界は別々に発展をとげてね。どうも、そちらの世界にも、オスカルとおれが住んでいて、こちらの世界にもオスカルとおれが同じように住んでいて、その二人があの鏡を通して精神だけ入れ替わってしまったらしいんだ」 ほら、君も鏡が異世界につながっているって話しをしていただろとアンドレが補足すると、また例のごとく、ふーんと曖昧なあいづちを打って、オスカルは先を促した。 「同じ時刻に、こちらの世界とそちらの世界の人間が、あのゲートになる鏡の前に立つことで、入れ替わりが起こるらしいんだ。誰にでも起こるのかは不明だけどね。だから、また同じ時刻にお互い鏡の前に立てば、これも仮説だけど、元に戻れる可能性が高い」 過去と未来でなく、異世界であると説明したことを除けば、嘘は言っていない。アンドレはオスカルの顔色をうかがう。こんな説明で納得してくれるだろうか。アンドレ自身、確証がもてない。銀色のカランから水滴が一粒こぼれ落ちて、シンクの中にポトリと落ちた。 オスカルが目を伏せた。 「話は理解した」 ジャルジェ家に伝わるという伝説のひとつに、話が符合していたからだろうか、意外なほどあっさり納得してくれて、アンドレはほっと胸をなでおろした。だが、彼女は腕組みをしたまま、ゆっくりと目を開くと、再び鋭い目つきで彼を見つめた。 「で、おまえは一体どうやって、そのことを知ったのだ?」 それは手紙で……と喉まで出かかって、アンドレは言葉を飲み込んだ。過去から届いた手紙のことを明かすわけにはいかなかった。手が次第に汗ばんでくる。二人とも黙りこんで互いの出方をうかがう。アンドレの背後から、かすかに冷蔵庫のモーター音が聞こえてくる。 正直、まだそこまでは考えていなかった。手紙を読んでから、まだ数十分しかたっていないのだ。その間も、部屋の片付けをしていて、今後についてじっくり考える暇などなかった。小説で言うなら、アイデアのメモ書きをしただけで、まだ十分なプロットを練れていない段階だ。しかし、何とか話をつづけて、辻褄を合わせなければならない。たとえ下手なアドリブの連続だとしても、幕が上がった以上、舞台は最後までつづけなくては。 「その……それはだな、君が寝ている間に奥の部屋の鏡を調べたんだよ。そしたら、そう、声が聞こえて。あれは、おれの知っているオスカルの声にまちがいない。それで、この状況について……話してくれたんだ。すぐに聞こえなくなったけれど、確かに今夜9時に再び鏡の前に立ってみるからと言っていた」 とっさに思いついた嘘をつく。アンドレは動揺を顔に出さないだけでも精一杯だ。 オスカルはじっとアンドレの顔を見つめている。青い瞳はいつもより眼光が鋭く、彼の瞳の奥から真実を読み取ろうとしているかのようだった。目をそらしたら嘘を見抜かれてしまいそうで、アンドレは動くことができない。ごくりと唾を飲みこんだ。また冷蔵庫のモーターの音が聞こえる。 「わかった」 ふいにオスカルの方から視線を外した。 「信じよう。おまえがわたしを騙しても、何の利益もないしな」 飲み物を頼むと言い残して、キッチンから出て行く後ろ姿を見て、アンドレは最大の難関を突破したと思った。歴史を守るための嘘を交えながらではあるが、手紙に書いてあった内容を、まちがいなく正確に伝えることができた。 あとは数時間、この部屋の中で待てばいいだけだ。彼は、どうやって過ごそうと考えながら、ホーローのミルクパンを取り出し、ミルクをそそぐとコンロであたため始めた。 アンドレが淹れたてのショコラを持ってリビングに行くと、オスカルは窓辺に立っていた。美しい透かしの入ったレースのカーテンを少しだけ指で持ち上げ、窓外を見下ろしている。 甘い香りに気がつくと、ゆっくりと振り返る。窓枠の緑色に彼女の髪の色が映え、デザインのモチーフに使われている月桂樹の葉が揺れたような錯覚を覚えた。 「メルシ、とてもいい香りだ」 アンドレがトレイをテーブルの上に置くと、彼女はソファに腰かけ、カップを静かに持ち上げ、口に運んだ。 こちらのオスカルが好きな飲み物のひとつだから試しに淹れてみたのだが、その満ち足りたような表情に、正解だったなとアンドレは思った。それでなくとも、甘いものは心をくつろがせるのに役に立つ。 「うん、うまい。温度もちょうどいいし、アンドレの淹れた……あ、おまえもアンドレだったな。わたしの世界のアンドレの淹れた味に近い」 それはどうも、とお礼を言うと、オスカルはもう一口、口にふくんだ。 ゆったりと自分の好きな上質なものに囲まれていると、オスカルはいつも、こんな表情を浮かべる。それは高価なビスクドールが微笑んでいるようにも見え、見つめていると、なんとも幸せな気持ちにさせてくれる。 こうしていると、彼女が自分の知っているオスカルでないとは、信じられなくなりそうなくらいだ。 「なんだ?わたしの顔に何かついているのか?」 穴のあくほど見つめられているのに気がついて、オスカルが困ったように言う。アンドレがごめんと謝る。これもいつもと同じだ。 「アンドレ、さっき窓から、馬の引いていない色とりどりの馬車のようなものが行き過ぎるのが見えたのだが、あれは何だ?」 「auto(オト)と言ってね。馬のかわりに機械が車輪を動かして走るんだ」 魔法みたいだなとオスカルが言うので、アンドレが、まあそんなものかなと答えると、オスカルは、またカップから一口ショコラを飲んだ。 「さっきの音楽といい、こちらの文化は、わたしの世界とは全く違うが、好きか嫌いかは別として、非常に興味深い」 「気に入っていただけましたら、光栄です」 くつろいだ雰囲気の中の他愛もない会話に、アンドレが少しおどけた口調になる。オスカルはだまって微笑んだまま、ショコラを味わいつづけている。カップが空になった頃をみはからい、アンドレがお替りは、と尋ねかけたところで、彼女がつぶやいた。 「もっと見てみたいな」 「え?」 オスカルの青い瞳が、天井のシャンデリアの輝きを受けて光っている。好奇心いっぱいの表情を浮かべて。 「約束の時間は、たしか晩の9時だったな、なあ、アンドレ」 彼女は壁にかかっている時計の文字盤を確かめた。短針はⅡの数字の上にあり、もうすぐ長針はⅩⅡのところにたどりつこうとしているところだ。 風向きが怪しくなっていたことに、アンドレは初めて気がついた。あの時計も隠してしまえばよかったか。 黙っておとなしくショコラを飲み干す間、彼女は何をたくらんでいたのか。おだやかな表情の裏で、彼女の中では、きっとつむじ風が吹いていたに違いない。 (つづく) |
||||||
|
||||||