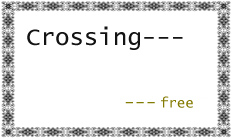 |
||||||
オスカルがソファから立ち上がった。アンドレは座ったまま、彼女の顔を見上げるようにして、念のために訊く。 「ど……どこへ?」 「外へ」 オスカルは、何をわかりきったことをと言わんばかりに答える。 「Le temps est de l'argent(時は金なり)だぞ、アンドレ」 アンドレは内心、無駄だと思いつつも最後の抵抗を試みた。 「外出するのは極めて危険だし、万が一にも時間に間に合わなかったら困るし……」 アンドレ自身も説得できるとは思っていないので、声に力はなく、最後は消え入るようだった。彼の煮え切らない態度に、オスカルは少し苛立ちを覚え始める。 「おまえが行きたくないと言うのであれば、ここに残るがよい。わたしは一人でも行くぞ!」 「お、おい、待てよ!」 オスカルはくるりと美しいターンでアンドレに背を向けた。やや胸を逸らせて真っ直ぐに伸びた背中は、そのまま、すたすたと廊下に通ずるドアに向かい、彼を振り返りもせずにさっさと出て行ってしまった。 アンドレはその潔いまでの行動のすばやさに唖然としたが、すぐに我に返ると、自分のコートと、クッションの上に置いてあったオスカルのストールを掴み、慌てて後を追った。彼女を見失うわけにはいかない。 “あまり遠くに行かないでくれよ、頼むから” そう願いつつ、よろけるようにして廊下に出てエレベーターホールまで走り、止まろうとした地点から勢い余って二、三歩勇み足を踏む。 彼女がエレベーターの脇で腕を組み、上品な色合いの壁紙に悠然ともたれかかって、彼を待っていたからである。 「遅い」 切れ長の目を半ばだけ開いて彼をにらみつける。アンドレが追ってくることなど計算済みだったわけだ。 アンドレは深くため息をつき、ひとりごちた。 「そもそも主導権を握ろうとしたことが、まちがいだったんだよな」 現代の彼女に対しても、いつもそうなのだから。先制したつもりでいても、いつの間にか攻守が入れ替わって、知らず知らずのうちにオスカル主導で動いているのに気付く。気付いたところで、どうしようもない。そこには、ついつい彼女が動きやすいようにサポートしてしまっている自分がいるのだから。 「何をぶつぶつ言っているのだ!行くぞ」 アンドレは観念してエレベーターの扉を開け、彼女に乗るように促した。彼女は彼の顔をちらりと見て、少し不安そうな表情を見せた。おそらく見慣れない狭い箱状の空間に本能的に恐怖を感じたのだろうと、アンドレは手を差し伸べたが、オスカルはそれを無視すると、一人で箱の中に足を踏み入れた。アンドレも乗り込んで地上階のボタンを押す。エレベーターはゆっくりと下降し始めた。 黙って乗っていると、隣にいるオスカルの緊張している気配がアンドレに伝わって来た。 オスカルのアパルトマンのエレベーターは、機能的にはもちろん制御もセキュリティも最新のものに変更されていたが、建造された当初のものを補修して使用しており、外観や使用方法は昔そのままで、21世紀にはレトロに映る。 だが、18世紀に生きた人間から見たら、得体の知れない機械に見えるに違いない。フランスにエレベーターが普及し始めたのは、エッフェル塔が建てられた後だから、かなりアンティークな外観の代物といえど、彼女には全く馴染のないもので、目新しく映るし、その閉ざされた空間に身を置くのに不安を感じるのは無理もなかった。 かすかに上方に向かってかかる力に、知らず知らずのうちによろめいて、彼女はアンドレの肩に軽くぶつかった。はっとしてすぐに一歩分横に離れ、足を肩幅に開いて立つ。 やがて、わずかな揺れと共にエレベーターは停止した。アンドレがドアを開けると、彼女は当然のように先に下りて、わずかに紫がかった赤の絨毯の上に一歩を踏み出した。 さきほどのコンシェルジュが、いってらっしゃいませジャルジェ様、と恭しく挨拶すると、オスカルは目だけで挨拶を返し、まっすぐに正面玄関に向かった。この辺りはさすが堂に入っている。 季節はノエル直前も直前の12月。閑静な住宅街は、シャンゼリゼ通りのような繁華街の派手さはなかったが、それぞれに趣向をこらしたリースが戸口に掲げられ、室内がノエル用オーナメントで上品に飾られているのが、窓から見えていた。人通りはそう多くはなかったが、オスカルは、通りを行き交う人々や車を物珍しそうに見つめていた。極力表情には出さないように努めているものの、アンドレには彼女の心が手に取るようにわかった。 「で、どっちに行く?」 アパルトマンの前から一向に動こうとしない彼女にアンドレが尋ねると、辺りの景色に気を取られていた彼女は我に返って、咄嗟に指さしながら言った。 「こっちだ」 街の地理も、自分がどこにいるのかすら全くわからないはずなのに、あくまでもアンドレに主導権を握らせることを潔しとしないらしい。オスカルは当てずっぽうに西へと進路を取っていた。言ったが早いか、アンドレが付いて来ているのかどうかも確かめずに前に進む。やはり、さっきと同じ、胸を逸らせた真っ直ぐに伸びた背中で。彼は、きっと付いて来るものと信じて微塵も疑っていない。ずんずんと遠ざかっていく背中が可愛らしく見えて、アンドレは笑いをこらえながら、それを追った。 オスカルの住むパリ16区の西側には、863ヘクタールの広大なブローニュの森が広がる。アンドレは、パリの中心部に行くよりは、いくぶんかマシだろうと内心ほっとしつつ、早足の彼女に少し離れてついて行った。 オートゥイユ通りを数百メートル進み、ポルト・ドートゥイユ駅付近までやって来ると、木々が間近に迫ってくる。 「アンドレ、ここは?」 足を止めて、オスカルが尋ねた。 「ブローニュの森だよ」 アンドレが答えると、オスカルは目を丸くした。 「わたしの世界にも、同じ名前の森がある」 アンドレは、ぎくりとして、心の中でしまったと舌打ちをしたが、彼女にはここが未来のパリだと疑い出した素振りは見えなかった。彼の作り話を頭から信じ込んでいるからかもしれない。アンドレは胸をなでおろす。 「平行世界なんだから、同じような地名はいくつもあると思うよ。オスカルとおれだって、こっちに存在しているくらいなんだから」 アンドレがフォローを入れると、オスカルはいくぶん口をとがらせ、ふーん、そうかとまた、例の如く相槌を打ち、それ以上は掘り下げて尋ねては来なかった。 「わたしの住む世界には、ブローニュの森の他にも豊かな森があって、お子様がお生まれになる前は、よく王妃さまのお供をしたものだ」 オスカルは一瞬目を伏せてから、再び顔をあげ、記憶をたぐるように視線をさまよわせた。 「ヴァンセンヌの森、フォンテーヌブロー、……ムードン………」 最初は昔を懐かしむように目を輝かせていたオスカルの表情が、そこまで来て少し曇る。 「衛兵隊に転属してからは、王室とは一定の距離を置いていて…お供することもすっかり無くなってしまったが。今は、来年開かれる三部会に備え、それどころではないしな……。束の間のわたしの誕生日に休暇を頂戴して、父上、母上、姉上たちと過ごすようにと、まったく、アントワネットさまは……」 そう言われてアンドレは、彼女がどの年からやって来たのかを初めて知った。三部会は革命が起きた1789年に開催されたはずだから、目の前の彼女は、その前年のノエルからやって来たことになる。パリは、いやフランス全土が重税に疲弊し、不作が重なって民衆は飢えに苦しんで、世情は荒れて切迫する一方だった時期のはずだ。 はるか遠くに視線を泳がせていた彼女が尋ねた。 「では……では、この世界には、ベルサイユもあるのか?」 アンドレが力強く頷く。 「ああ。ここから20キロほど向こうに」 アンドレは西の空を指さした。 “20キロ”と言ってしまって初めて、それが彼女の生きた時代の後、ナポレオン一世が定めた度量衡の一つだったことに気づく。いろいろ説明することは憚られたが、彼女にはその単位にピンと来なかったものの、距離など細かいことは無視しても、ベルサイユという空間が存在することに安堵を覚えた表情が窺えた。もしかしたら、自分自身がベルサイユとパリを往復した時の感覚をあてはめていたのかもしれない。オスカルは、かすんだ空の向こうを何も言わずに見つめていた。午後に入って少し雲が出始めていた。 「アンドレ、あれは何だ?」 オスカルが空に浮かぶ飛行機を見つけた。白く尾を引く飛行機雲が青空にくっきりと浮かぶ。アンドレが、あれは空を飛ぶ乗り物で、たくさんの人間が乗っているんだよと説明すると、彼女は目を白黒させた。 「こちらのオスカルは、あの乗り物を操縦する仕事に就いているんだ」 空に向かって右手を伸ばし、人差し指を立てて、飛行機雲の軌跡を追いながら補足すると、、いっそう彼女の目が大きく見開かれる。アンドレは説明をつづけた。 「こっちでは、女性でも、どんな職業につくのも自由なんだ。才覚さえあれば、国を動かす政治家にも金持ちにもなれるチャンスだってある。フランスで現在一番の金持ちは、某化粧品会社の女社長だっていう話だ」 身分の差だってないしねと言うと、オスカルは一層目を見開いた。空飛ぶ乗り物なぞよりも、こちらの方がずっと驚きだったらしい。凛と閉ざされていた唇が開き、小さく声がもれた。 「自由……」 長く尾を引く飛行機雲は、水色のカンヴァスに白い線を引きながら、悠々と大空を横切っていく。オスカルはじっと空を見上げていた。アンドレの目に映る、空の青さと彼女の金色の髪の対比。深い彼女の蒼の瞳は、何を映し出しているのだろうか。 (つづく) |
||||||
|
||||||