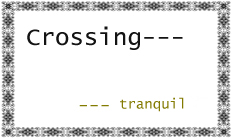 |
||||||
二人はポルト・ドートゥイユ通りをさらに西に向かって歩いていた。 オスカルは、ベルサイユに行くことはできないかと尋ねたが、アンドレもさすがにそれには首を縦に振れなかった。彼女に見せてはならないというだけでなく、時間的に無理があった。 オスカルはそれから無言のまま歩きつづけている。アンドレは少し離れて後ろをついていく。彼女の背中は怒っている風には見えなかったが、会話のきっかけを掴みかねて、アンドレもやはり黙って歩いていた。 オスカルが立ち止まったので、アンドレは彼女に追いついた。彼女は、正面に円柱が何本かそびえ立つ建物を見上げている。円柱には蔦がびっしりと巻きついていた。ローラン・ギャロスだ。 「ここはテニス・コート」 ようやくアンドレは会話の糸口を見つけて話しかけることができて、何だかほっとする。 いつもの二人になら、沈黙はどうということはなかった。いっしょにいても、別々のことをしていたり、ただ黙って傍にいることはあったが、それでもお互い安心していられる。しかし、今、オスカルの中にいるのは、彼がよく知らないオスカルで、沈黙がずっと、どこまでもつづくのは決まりが悪かった。 「テニス?」 「え……と、糸を縦横に張ったこんな形の道具で、ボールを打ち合うスポーツだよ」 アンドレは両手でラケットの曲線を描いてみせる。 「ジュー・ド・ポームのようなものか。ベルサイユにも競技場があったよ」 オスカルは眩しそうに額に手をかざした。見上げていた建物の向こうから、もうだいぶ西に傾いた太陽の光が差していた。 彼女の言葉に特別な感慨は感じられなかった。そのベルサイユにあるジュー・ド・ポームの競技場で、どんなことが起こったか、今、ここにいる彼女はまだ知らない。アンドレの左胸の奥がなぜだか、ちりりと痛んだ。 彼女から視線を外したアンドレは、通りの向こう側にあるブローニュ門に気づく。ブローニュの森に入るための、いくつかの門のうち、一番南にある門だ。 「せっかくここまで来たんだし、森の中を歩いてみないか?」 アンドレが誘うと、オスカルは素直にこくんと頷いた。 パリの西に広がるブローニュの森。 かつては、うっそうと樹木の生い茂った治安もよくない場所であったが、パリが大改造された際に整備され、今は森というよりは公園と呼ぶにふさわしくなっている。 美しい庭園や湖のほか、遊園地にカフェまであり、凱旋門賞で有名なロンシャン競馬場、そして、さきほどオスカルが見上げていた、全仏オープンの行われるテニスの聖地、ローラン・ギャロスのある場所としても知られている。 夏には緑の葉が生い茂って、きらきらと木洩れ日が遊び、陽光を求めてパリ中から人が集まる場所だが、冬の今は、閑散としていた。 ほとんどの木は落葉して、陽光は朱夏の力強さを失い、ヨーロッパ特有の陰鬱さを伴った玄冬が、ここにも居座ってしまっている。 カシワだけは、丸裸になってしまうのを恥ずかしいとでも思うのか、枝に茶色く枯れた葉をつけたまま立っていた。役目を終えたはずの葉は、すっかりひからびてしまっているにも関わらず、春に新芽が出て自分達の居場所を明け渡して落ちていくまで、木枯らしに吹かれながらも頑固にそこに留まっている。 「わたしの知っているブローニュの森とはずいぶん違う。それに、何だか”森”と呼ぶのは違和感がある」 オスカルは遊歩道に落ちていた枯葉を一枚、拾い上げた。 「部屋の中も街もそうだが、ここも明るすぎるくらい明るい」 彼女の感想に、“地上から闇を取り払うことを使命にしているのが現代文明なのかもしれない”などと、アンドレは、いつものように語らいたくなったが、そうするわけにもいかず、口には出さなかった。 わあーっと鬨の声のような歓声が聞こえて、二人は振り返った。 「オートゥイユ競馬場かな。まだこの時期でもレースをやってるみたいだね」 オートゥイユは障害レースがメインで、12月の寒い時期でもまだ競技が行われ、パリっ子を楽しませてくれている競馬場だ。 「近衛隊にいた頃、ルイ16世陛下がシャン・ド・マルス競馬場で王侯貴族のために競馬を開かれて警護に当たったことがあるが、どうも、馬を賭け事の道具として使われるのは好かなかったな」 そもそも賭博自体が性に合わないからな、そう言って、彼女は眉をひそめた。 おまえは賭け事をするのかと聞かれ、アンドレは肩をすくめる。 「学生の頃、友達が学校一の美人を口説き落とせるかとか、そんなことで賭けをしたことはあったけど。どうもギャンブルには向いていないみたいで、宝くじだって当たったことはないし」 「で、結果はどうだったのだ?」 「何の?」 「美女を口説き落とせたか……どうかさ」 彼女は子供っぽい悪戯な表情を浮かべている。アンドレには少々、意外な発言だった。聞きたいのはそこか。上から物を言う上に、軍人だというから、もっとお堅いイメージがあったが。軽い驚きとともに、アンドレには彼女が急に身近に感じられた。 「そいつを応援したくて、一人だけ“うまくいく”方に賭けて。……えらい目にあった」 アンドレはまた肩をすくめてみせた。 オスカルは「おまえらしいな」と言って、さも愉快そうに大笑いした。 オスカルがあまりに長く、楽しげに笑いつづけるので、さすがにそこまで笑うことはないだろうとアンドレが不満を口にすると、オスカルは笑うのをやめた。 だが、彼の苦情を聞き入れたからというわけでもなさそうで、視線がアンドレを通り過ぎて、木立の中にそそがれている。 「アンドレ、馬が」 言われて、アンドレがそちらを見ると、木々の間に白い尾が揺れているのが見えた。競馬の話をしていたからというわけではなかろうが、鞍と手綱を付けた乗馬用とおぼしき馬が一頭たたずんで、様子を伺うように、こちらを見ていた。 やがて、森の中央の方から男が走って来て、木立のかなり手前で止まった。馬を驚かさないように、ゆっくりと近づいていく。馬の轡を捉え、木立から遊歩道に引っ張り出すことに成功したが、白葦毛の馬は、そこで後ろ足を蹴り上げるようにして暴れ出した。手綱を持った男が必死に落ち着かせようとするが、馬はかえって興奮して、男を振り払おうとする。 男が身の危険を感じ、手綱を放そうとしたとき、御しかねた男の手の隣に、優美な仕草で白い指が伸びた。 いつの間にか近づいていたオスカルの手だった。 彼女が手綱を強く引くと、馬は先ほどの暴れようが嘘のように大人しくなったが、まだ鼻息は荒く神経質そうに鼻を鳴らしていた。 「名前は?」 「メルキオール・シャロン……」 聞かれて、半ば呆然とした男が答えた。 「そなたの名前ではない。馬の名前だ」 若い男は、顔を赤らめた。この状況で聞かれるとしたら馬の名前の方だろうと、自分でも気がついて恥じ入ったらしい。 「ファリンヌ……です」 オスカルは馬の名前をささやきかけながら、しっかりと轡を握りつつ、その鼻面をなでた。 だんだんと馬の様子は安定し、神経質そうに動かしていた耳も落ち着いていった。 「あ、ありがとうございます。とても気難しい馬で、こうやって脱走ばかりしてて」 ブローニュの森にはいくつかのスポーツ施設がある。乗馬クラブやプールを備えた会員制のものがほとんどだが、どうやら馬は、そのひとつから逃げ出して来たもののようだった。 馬が静まったのを見て、メルキオールは手綱を受け取ろうとした。しかし、馬は男を侮っているのか、轡を取られるのを嫌がって再び暴れ出しそうな気配を見せる。 「乗っても構わないか?」 オスカルが尋ねると、意外な申し出にメルキオールは驚きつつも承諾した。 「鞭を」 男の方は振り返りもせずに、まるで控えている使用人にするかの如く、オスカルは手だけを伸ばす。メルキオールが求められるままに乗馬用の鞭を渡すと、彼女はあぶみに左足をかけ、それからひらりと鞍に跨った。馬場の場所を尋ねて一鞭くれると、まるで愛馬にまたがっているかの如く、駆け足で走らせて行ってしまった。 後には、取り残された男が二人、彼女の自然体でまっすぐに伸びた背中を見送っていた。 「あの女性は、調教師か、それとも馬術競技の選手か何かですか?」 「軍人です」 アンドレが答えると、メルキオールは、へえ、そうなんですかと腑に落ちないような、感心したような複雑な顔をしてみせた。 二人がやっと追いつくと、オスカルはまだ野外練習場でファリンヌを走らせていた。 並足からトロット、そしてギャロップへと的確な指示を送り、馬は従順に従っている。逆光になると、人馬が黄金色に縁取られた一つの影となって、ギリシャ神話のケンタウロスのように、一つの生き物であるかのような錯覚すら覚える。 いつの間にか人だかりが出来ていた。その華麗な騎乗はもちろんだが、ブロンドの豊かな髪をひるがえすオスカルの姿は、それだけで人目をひいた。 訓練によって生み出された動きと、人間が真似することのできない自然が生み出した造詣美の見事な調和――。アンドレも知らず知らずのうちに、息をひそめるようにしながら見とれてしまっていた。 アンドレに気がつくと、オスカルは手綱を強く引いて、馬を止めた。鞍から下りて手綱を引いて近づいて来る。 「あの馬があんなに素直なの、初めて見た」 メルキオールはしきりに感心している。この乗馬クラブの厩舎で働き始めて3年になると言うが、ファリンヌは気性が荒く、乗り手を選ぶ馬で、なかなか乗りこなせる者はいなかったらしい。上級者になると、そこがいいと言って好まれているというのだが。 「この馬は、ちゃんと調教すれば、もっとよくなるぞ」 メルキオールに手綱を渡しながら、オスカルが息を弾ませて言う。礼を言いながらメルキオールは慎重に受け取る。一通り気持ちよく走った後だからか、今度はファリンヌも暴れることなく大人しくしていた。 オスカルが最後に、いい子だなと馬の鼻面をなでてやると、ファリンヌはブルルと嬉しそうに鼻を鳴らした。 立ち去ろうとすると、メルキオールが、よかったらまた寄って下さいと声をかけた。オスカルは振り返って「ああ」と極上の笑顔を返した。 メルキオールはそれで有頂天になっていたようだが、このオスカルがここに来ることは、おそらく二度とないだろう。アンドレには、その笑顔が何かを断るときの彼女の常套手段だとわかって、多少の哀れを感じる。 馬場からかなり離れてからオスカルが言った。 「どうもこの体では、いま一つ、いつもの調子が出ないな。それに、これしきで息があがるとは」 自分の肩に手をかけて首を左右に倒したり、太腿の辺りをさすったりしている。 現代のオスカルも小さい頃から乗馬をたしなんではいると聞いているが、日常的に馬を疾駆させている軍人のオスカルに比べれば、馬をコントロールするための筋肉が鍛えられていないのは当たり前で、日常動作では感じなかった違和感を感じたのだろう。 「元に戻ったら、もっと体を鍛えた方がよいと言っていたと、そのように伝えてくれ」 自分で自分に伝言するのも奇妙なものだとアンドレは思ったが、かしこまりましたと承知した。 日はかなり西に傾いてきていたが、まだ日没までには少し時間があった。 二人はしばし、そのまま、そぞろ歩きすることにした。 公園のほぼ中央に位置するアンフェリウール湖のほとりまでやって来ると、アンドレは湖の中の島にカフェを見つけ、あそこで休まないかと提案した。 しかし、オスカルは別の方向を指差した。 (つづく) |
||||||
|
||||||