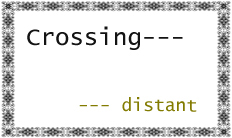 |
|||||
ゼウスの娘モイライは、時を司る、運命の女神達。 ラケシスは運命の糸を割り当て、クローソーがその糸を紡ぎ、アトロポスはその糸を断つ。 運命の女神の定めは、神々の王ゼウスですら抗うことができぬ。 ブリュッセル南駅、午前7時37分発のタリスの切符を、アンドレは手にしていた。 日の出前だ。ようやく白み始めた空では、星座達が眠りにつこうとしている。ぴんと張り詰めた冬の空気に、吐く息が白い。 彼は、プラットフォームを薄ぼんやりと照らす電燈の下で、手元の切符を確認し、自分の乗車する号車を見つけると、すばやく乗り込んだ。もう発車まで、そんなに時間がなかった。 彼の乗り込んだのは二等車だった。車内は、通路を挟んで座席が二つずつ並んでる。一等車に比べてシートが狭く、背もたれの頭の部分が固くて、座り心地はいまひとつだが、ブリュッセル―パリ間を、タリスはわずか1時間22分で結んでいるから、一等車でなくても十分だった。 指定の席につくと、彼はシートに深く腰を下ろして、窓の外を眺めた。一昨日から今朝までの忙しさを思い返す。予期せぬ出来事が次々と起こって、予定がめまぐるしく変わった。 しばらくすると、アンドレと通路を挟んだ隣の席に、小柄な老婦人がやって来た。老女は、荷物を頭の上の荷物入れに入れようとしたが、うまく収納することができずに困っている。 アンドレはすぐに立ち上がって、手助けをした。老婦人はアンドレに丁寧にお礼を言うと、どっこいしょとかけ声をかけて、シートに座った。 やがて、タリスは滑るように走り出した。 車両内には老婦人とアンドレ以外、誰もいなかった。 「明日はノエルだというのに、朝早くから、お互いに忙しいものだわね」 通路を隔てた席から、老婦人がフランス語で親しげに話しかけて来た。そうですねとアンドレが相槌をうつと、彼女はうれしそうに、とりとめもないおしゃべりを始めた。 彼女は、今までブリュッセルに住む長男夫婦のところに泊まっていて、これからボーヌに帰るのだという。近くには次男夫婦が住んでおり、ノエルはそこで過ごすのだそうだ。ボーヌはスイスに程遠からぬコート=ドール県にあり、郡庁所在地である。 アンドレがブルゴーニュ・ワインで有名なところですね、と話題をふると、老夫人は顔をほころばせ、うちでもワインを作っているの、亡くなった夫の跡をついで、今は次男一家がねと、答えた。まだときどきは畑での作業を手伝うらしく、縮れた白髪の下の肌は、永年、農作業で紫外線にさらされて来たのだろう。染みだらけで皺が多く、老けてみえたが、それがかえって彼女に素朴なあたたかみを与えているとアンドレは思った。 彼女はひとしきり話し終わると、今度はアンドレのことが聞きたくなったらしい。 「あなたは?どうしてこんな日の、こんな時間に?」 「実は……その、恋人へのプレゼントを買って、これから急いでパリに戻るところなんです。ブリュッセルでは、いろいろあって」 老女の人のよさに気を許したアンドレは、ありのままを話した。旅の閑暇を慰めるにはちょうどいい長さの話だったし、この3日間の自分の苦労を、誰かに少しだけ聞いてほしかったというのもある。 「まあ、ぜひ聞かせてちょうだいな、そのいろいろを」 老婦人は好奇心いっぱいの目で彼を見つめた。促されて、アンドレはこの3日間にあった出来事をはじめから順を追って話し始めた。 ※タリス(Thalys-PBKA) パリなどから、ベルギーのブリュッセル、オランダのアムステルダム、ドイツのケルンなどを接続する国際高速列車。フランスのTGV <http://ja.wikipedia.org/wiki/TGV>を基本にしている。 Thalys-PBKAとは、Paris、Brussels、Koeln、Amsterdamの頭文字を取って並べたもので、Thalysの中でも四カ国に乗り入れ可能な車両を指す(信号システムと電源が四カ国対応)。 |
|||||
アンドレが、とある古美術商に探してもらっていた品物が、ベルギーのブリュッセルにあると知ったのは、12月22日のことだった。それは、恋人の誕生日に贈る初めてのプレゼントになるはずのものだ。彼女の誕生日は12月25日。今は仕事で異国の空の下のはずだが、誕生日の翌日にはパリへ、彼の元へ戻って来るはずだ。いっしょにその日を過ごすことは叶わないが、それを、記念に彼女に渡したかった。二人が巡り会い、こうして一緒にいられるという記念に。 うまくいけば日帰りできると思ったが、念のために一泊分の着替えと旅行用の洗面用具などを小ぶりな皮製のトランクに詰めて、家を出た。 パリ北駅を出発し、ブリュッセルに到着したのが午後4時過ぎだった。 アンドレは、電話で聞いた番地のメモを見ながら、その品を所有している店を探して、初めての街をさまよった。 ベルギーでは北部でオランダ語、南部ではフランス語が使われているが、ブリュッセルは2言語併用地域だ。英語も通じる。道を訊ねることは容易だったし、その店は、駅から遠くない比較的大きな通り沿いにあったので、到着してから1時間もたたないうちに辿り着くことができた。 しかし店を見つけた喜びも束の間、アンドレは風雨にさらされた入り口のドアの前で立ち尽くすことになった。ドアノブにかけられたボードには、 愛想のないボールドのゴシック体で“CLOSED”の文字が書かれており、通りを吹き抜ける風に揺らされて、カタカタと音を立てていた。 パリの古美術商は、今日行けば開いているはずだからと確かに言っていたが、早仕舞いしてしまったのだろうか。 メモに書いてある電話番号にかけてみるが、アンドレの目の前にある店の中から、ベルの音が、いつまでも虚しく鳴りつづけるばかりで、一向に誰も出る気配がない。 仕方なく、翌日出直すことに決めた彼は、辺りを見回した。通りを隔てた、はす向いに小さな3階建てのホテルがある。今夜の宿をそこに求めることにして、道を横切った。 そこを宿泊先に決めたのは、骨董品店から近いこともあるが、フランス語で書かれた看板が目に入ったからだった。異国で出鼻をくじかれた彼にとって、母国語のもつ温かさは多少のなぐさめになった。 布製のひさしの下の白いドアを開けると、真正面にフロントがあって、その中に二十歳前後の青年がいた。フロントと言っても粗末な木のカウンターがあって、そこにフロントと書かれたプレートが載せてあるだけの代物だったが。 アンドレが今夜泊まりたいのだが、と言うと、青年は見ていた小型テレビから視線をはずして、部屋の希望を聞いて来た。 狭くてもかまわないから、通りに面していて、バス・ルームかシャワーのあるシングルを、朝食付きでと彼が答えると、青年はカウンターの奥にある棚からルーム・キーを取り出して、アンドレに渡し、朝食は7時〜9時までだよと、ぶっきらぼうに言った。 部屋は、剥き出しのタイルの床にテーブルとソファ、それにベッドがあるだけの簡素な内装だったが、明日の朝まで暖をとれて、ゆっくり眠れればいい。近くのレストランで夕食を済ませたアンドレは、ベッドに腰掛けて携帯を確認した。着信はない。ふと、彼女に自分がブリュッセルにいることを知らせておこうかとも思ったが、そうなると、なぜ彼がそこにいるのかも説明しなくてはならなくなるだろうから、やめておこうと思い直した。何も知らせずに驚かせてやりたかった。 それに時差もあった。彼女は今、アジアを周遊するという金持ちマダム御一行さまに付いて行っている。あちらは今、早朝のはずだ。 彼女は多忙だ。ノエルも自分の誕生日もおかまいなしで仕事をしている。 トランクの中から読みかけの本を取り出すと、アンドレはベッドにごろりと横になって、しおりの挟んであったページを目で追った。しかし、数行読んだところで、すぐに彼女のことを考えてしまう。ちっとも先に進まなかった。 彼女は、自分のプレゼントを見たら何と言うだろうか。彼女の顔を想像する。喜んでくれるだろうか。喜んでくれるといいが……。 彼女は風のように軽やかで、自分の意志のままに振舞う。踊る黄金の髪。生き生きと輝く深い蒼の瞳。アンドレにはそれが眩しいし、その自由さが彼女の魅力だと思う。だが、ときどき自分の腕をすり抜けてどこかに飛んで行ってしまうのではないかと思うことがある。 自分でもおかしいと思うのだが、常にそんな不安が彼の中心に巣食っている。 こんなにも初めての誕生日のプレゼントにこだわるというのも、少しでも二人の絆を確認しておきたいという見苦しい気持ちがあるからかもしれないと、彼は思う。 ふと窓の外を見ると、例の骨董品店の店内は真っ暗で、ドアのボードは相変わらず風に揺れていた。 アンドレはカーテンを閉めると、べッドに再び寝転んで、先ほどの本に手を伸ばした。 翌日はよく晴れた日だった。昨日と同じで風が強い。 アンドレはホテルの一階にある小さなテーブルが4つだけのレストラン・スペースで食事を済ませると、フロントに向かった。昨晩の青年がまだ眠たそうな顔でそこにいた。伸びかけの赤毛に、少し寝癖がついている。 アンドレは支払いを済ませると、彼に言った。 「実は、向いの骨董品店に用があって昨晩パリからやって来たんだけど、昨日は早仕舞いしてしまったようでね。店が開くまで、部屋をそのまま使わせてほしいんだ。もちろん、追加の料金は支払うよ」 彼がそう言うと、青年は驚いたような顔をして言った。 「ドームさんの店のこと?それなら、年明けまで休みにするって言ってたよ」 アンドレの顔色が変わる。それでは、年内いっぱい品物が手に入らないということになる。タイミングを外しては、彼の計画が台無しだ。わざわざここまでやって来た意味もなくなる。 「その自宅の電話番号、住所でもいい!知っているなら教えてくれ!!」 掴みかからんばかりに、カウンターから身を乗り出したアンドレに気圧されて、青年は一歩あとずさりした。 「それは、それはいいけどさ。何かあったら、連絡してくれって頼まれてるし。……でも店は開けてくれないと思うよ。ここから30キロ離れた娘さんのところに行くって言ってたから」 それはどうにかするから、とアンドレが頼み込むと、青年はカウンターにあったメモ用紙を一枚破り取り、ボールペンを走らせて、アンドレに渡した。 アンドレは、早速、レストランの椅子に腰掛けると、書かれていた番号を携帯に打ち込んだ。呼び出し音がしばらくつづく。少し苛立ちながらも辛抱して待っていると、やがて受話器を取る音が聞こえた。 ほっとして、名前と用件を伝える。最初に出た年配の女性が、お待ち下さいと言うと、くぐもった音が聞こえた。きっと送話口を手で押さえたのだろう。その向こうから「あなた!あなた!お客さんから電話よ」という声がわずかに聞こえる。 ほどなくして、張りのある声の男性が出た。 アンドレは、もう一度、丁寧に自分の名前と用件を伝えた。相手は、待っていたが来なかったので、昨日は店を閉めて帰ったと言った。 アンドレが、連絡をもらってすぐにブリュッセルまで飛んで来たが夕方になってしまったこと、どうしても25日までに品物を手に入れて、パリに戻りたいことを説明したが、相手は良い返事をしてくれない。わざわざアンドレとの約束を果たすためだけに、店を開けるのは億劫らしい。彼にしては珍しく、強行な態度で、約束したのだから店を開ける義務がある、あなたの信用問題にも関わるとまで言うと、店主は渋々承知して、では、イヴを家族水入らずで楽しんだ後の25日なら、店を開けてもいいと譲歩案を出した。 25日の午前中ならば、オスカルが戻るまでに十分パリに戻れる。アンドレは店主に突然の電話を詫び、厚意に感謝を述べると、携帯を両手で包むように持ちながら電話を切った。 気がつくと、カウンターの外に出て来ていた青年が、顛末を見守っていた。 「いったい何をそんなに急いでいるんだ?そんなに値打ちのあるものなのか?それとも、お客に渡す納期が迫ってでもいるのか?あんたも古美術商かなんかなの?」 アンドレのただならぬ様子に興味をひかれたらしい。立てつづけに質問を繰り出しながら、アンドレの隣のテーブルから椅子を引き寄せて来て、そばに腰を下ろした。 人目もはばからず、慌てて電話をかけたことに、アンドレは少し気恥ずかしくなったが、どうも説明せずには収まりそうにない。それに、ここにはあと2日世話になるのだ。親しくなっていておいてもいいだろう。 「実は、あの店にある、18世紀の懐中時計がどうしても欲しくてね。値打ち物といえば値打ち物なんだけど、個人的にとても興味があるってだけで。それと、おれの仕事は古美術商じゃなくて――」 そう決めたアンドレは、パリから来た理由を話し始めた。 彼女からの電話を受けたのは、その日の夕方だった。 ピエール――ホテルのオーナーの息子で、フロントにいた青年だ――のお勧めの場所を一通り回り、ホテルに戻って来て、二階につづく階段の踊り場まで昇ったときだった。 「オスカル?どうした?」 我ながら声が弾んでいる。うれしい秘密があって、打ち明けたいけれど打ち明けられないときは、こんな声になってしまうものだ。 「今、どこにいると思う?」 心なし、彼女の声も弾んでいるようだった。 「どこって……。東京、それとも北京?今はそれとも、バンコクだっけ?」 彼女が勝ち誇ったような声で言う。 「パリだ」 アンドレは一瞬、事態が飲み込めなくて絶句した。彼女は、たった今、シャルル・ド・ゴール空港に到着したばかりであること、今まで黙っていたが、彼と誕生日を過ごすためにスケジュールを調整して休暇を取ったことを、陶々と話した。 アンドレは聞いているうちに、何が起こっているのか整理できてきたが、まだ口がきけない。 彼女はこのところ、いつも以上に休みなく勤務につぐ勤務だったことを思い出す。彼女の体が心配で、少しは休んだ方がいいと口を出し、危うくケンカになりかけたこともあった。そうやってやっとの思いで、忙しくて毎年休めない時期に、休暇をもぎ取ったのだろうと、今になって分かる。 問題は、彼女がパリにいるのに、自分はブリュッセルにいることだ。 しどろもどろになって、今、自分がブリュッセルにいることを告げると、今度は彼女が沈黙してしまった。見えなくても、今、彼女がどんな顔をしているかは想像がついた。 「そ、そうか。では仕方がないな……。25日の昼頃なら大丈夫…か?」 やっとのことで気を取り直したのが、搾り出すような彼女の声から感じられた。 アンドレは済まない気持ちでいっぱいだったが、オスカルがそっけなく電話を切ってしまったので、それ以上、言い訳することもできなかった。 ツーという抑揚のない電子音が電話から聞こえる。 「それが、アンドレにとっての“個人的な興味”ってわけか」 立ち尽くすアンドレを、にやにやして、ピエールが下から見上げていた。 少しだけ迷った後、アンドレは階段を駆け下りると、玄関から通りへ出て行こうとした。その腕をピエールが掴む。 「ドームさんちに行くんだろ?30キロあるんだぜ。走っていくつもりかよ。だいたい道がわかるのか?今、タクシーを呼んでやるから、待ってなって」 言うが早いか、カウンターの電話を取り上げた。 市街地を抜けるまでに少し時間がかかったが、その後はスピードをかなり上げてスムーズに走らせることができ、車は1時間ちょっとでメモの住所に到着した。 ドアのベルを鳴らす。 中から自分と同じか、少し上くらいの女性が出て来た。アンドレが、昨日、ドームさんに電話した者ですがと告げると、奥に引っ込んだ。 少し怒ったようなドスドスという足音と共に現れたのは、名前どおり(ドームには、はげ頭という意味もある)、頭のはげあがった、ずんぐりとした体型の老人で、不機嫌そうにじろりとアンドレをにらむと言った。 「店はあさって開けると約束したはずだが、何の用かね?」 「実は、どうしても今日中に店を開けていただきたくて、お願いに来たんです」 アンドレが半開きのドアの隙間から頼み込んだが、相手はドアを広く開けて彼を迎え入れて話を聞く気はないらしい。 「今、ディナーの最中でね。悪いが帰ってくれないか」 そう言われても、ここまで来てしまった以上、簡単に引き下がるわけにはいかない。アンドレは閉められまいとドアに片手をかけて押さえた。 「あなた、どなたなの?」 奥から、今朝方、電話口に出た女性の声が聞こえ、奥から玄関の方に近づいて来るのが見えた。 「ああ、心配しなくてもいい。すぐに帰ってもらうから」 振り返ってそう答え、ドアを閉めようとしたが、アンドレが押さえつけているので、閉めることができない。 「ご迷惑は重々承知しています、でも…、どうか、お願い…できませんか!?」 手に力を入れているからか、声にも力がこもる。 「……聞いて差し上げたら?追い返すなら、それからでも遅くないでしょう」 温和そうな夫人が気の毒がって、夫を懐柔しようとしてくれた。 店主は夫人に言われて仕方なくドアを開けると、アンドレを招きいれた。玄関ホールに入れてもらえたアンドレは、店主と夫人の前で覚悟を決めた。 「あなたにとっては、重要でないことかもしれませんが、わたしにとってはとても重要なことで、ずっと明後日のために探しつづけていたんです、あの時計を……」 そう言って、時計を求めてベルギーまでやって来た経緯を打ち明けた。 すっかり話し終わった後も、店主は苦虫を噛み潰したような顔をしていた。“恋人への初めてのプレゼントに――”という理由が全く理解できないらしい。 対して夫人は、途中から、まるでドラマの主人公に感情移入するかのように、うっとりとしてアンドレの話を聞くようになり、 「いいじゃないの。クリスマスは施しをする日でもあるのよ。それくらいしてあげたらどう?」 最後には、すっかりアンドレの味方について、夫を説得してくれた。 夫人にそう言われては無碍に断ることもできず、店主はディナーを済ませた後でなら、と条件付きで承知してくれた。 アンドレは待ちますと答えて、ホールの椅子に腰掛けたが、夫人がせっかくだから一緒にディナーはいかがと声をかけてくれた。彼は一度は辞したものの、店主も一緒になって彼を招待したので断り切れなくなった。寒い玄関ホールで、すきっ腹を抱えて待っている人間を横目にして、自分達だけディナーを心から楽しめるほど、冷たい人間ではなかったようだ。 相手にはかなり無理をきいてもらっているのだし、どうせ終わるまで待たなければならないのは同じだからと、アンドレは承諾して、二人と共に奥の部屋に入って行った。 結局、アンドレが食事を終えて、ドームの店に戻って来られたのは夜の10時をまわってからだった。 テーブルには店主夫婦の他に、娘夫婦と3人の子供達がいた。着席したアンドレが自己紹介して、彼の職業が作家だと知ると、家族全員、彼の仕事に興味津々でいろいろと質問してきた。食卓を囲んで話に花が咲く。見知らぬ客人を最初は警戒していた子供達も、ディナーが終わる頃にはすっかり懐いてしまい、なかなかアンドレを帰そうとしなかった。 一刻も早くパリに戻りたいのはやまやまだったが、ごり押しを通してもらった手前、アンドレの方から帰りたいと言うこともできなかったし、ここで再び店主に臍を曲げられてしまっても困る。子供達が寝る時間までつきあうことにし、それからドームの自家用車で市内まで戻って来た。 店の金庫から、ドームがベルベットのケースを取り出した。その蓋を開けると、お目当ての時計が入っていた。 ようやく手に入れることができて、アンドレは安堵する。 店の戸締りをして通りに出たドームに礼を述べると、 「わしらも思わぬ楽しい時間を過ごさせてもらえたよ」 と言って、右手を差し出した。節くれだった大きなその手をアンドレは握り返す。ドームは車に乗り込むと、家族の待つ家へと帰って行った。 アンドレは彼を見送ると、昨夜から部屋を取っているホテルに向かった。もうこの時間では、タリスもない。明日一番の列車でパリに向かうことにする。オスカルも、誕生日までに戻って来れば納得してくれるだろう。 ピエールはまだ起きていて、カウンターでTVを見ていた。アンドレに気が付くと、振り返る。 「どうだった?」 アンドレは黙ってコートのポケットからベルベットのケースを取り出した。 |
|||||
辺りはすっかり明るくなっていた。ようやく顔を出した太陽が、右側の車窓で輝き、鳥の一群が弧を描いて、東の空に向かって飛んでいくのが見えた。 老婦人は言った。 「お互いがお互いを思いやって、まるでO・ヘンリーの『賢者の贈り物』みたいね」 彼女はきっと喜ぶと思うわ、少なくとも私だったら感激しちゃうと励ましてくれたが、果たして彼女は素直におれの帰還を喜んでくれるだろうかと、アンドレは少し不安に思っていた。 少し意地っ張りで、気の強い彼女の性格は熟知しているだけに……。 物語の結末のように、“この一見愚かな行き違いは、最も賢明な行為であった”と結ばれればいいがと思う。 列車は速度を落とした。枕木からの振動が強く感じられる。 もうすぐ、パリ北駅に到着だ。 (つづく) |
|||||
|
|||||